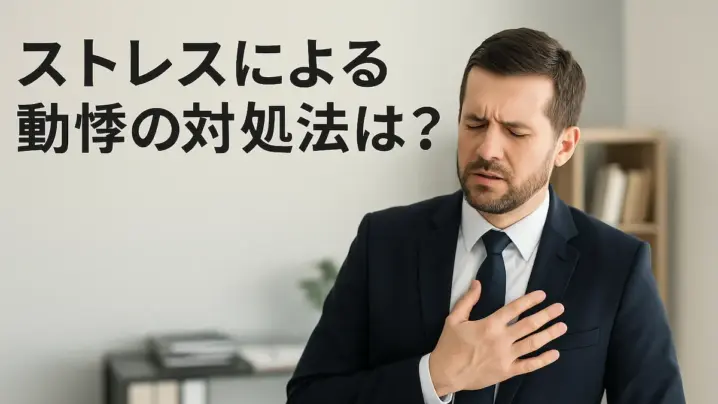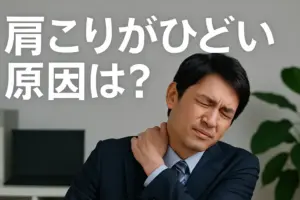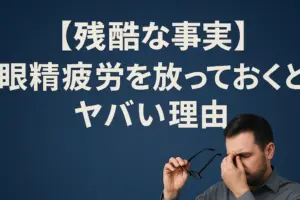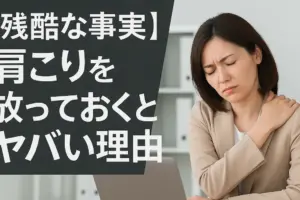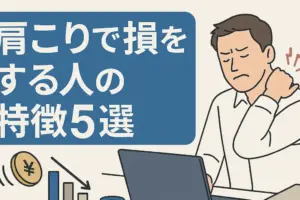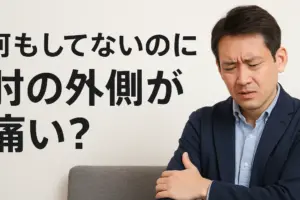最近、忙しい日々やストレス続きで胸のドキドキが止まらず、不安になることが増えていませんか?
結論をいうと、ストレッチを中心としたケアで落ち着きを取り戻すことは十分可能です。
実は、単発の対策だけでなく継続的な取り組みがカギ。この記事では、ストレッチの専門家が対処法から予防策まで詳しく解説します。
…………………………………………………………
目次(Contents)
1. 対処法

ストレスによる動悸は、突然起こることもあれば、じわじわと長期間続いてしまうケースもあります。
まずは「起こったときにどう対応すればよいか」という対処法を把握することが大切です。
ここでは、日常生活にすぐ取り入れられる具体的な手段を中心に解説します。
深呼吸と姿勢リセット
ストレスを感じたとき、呼吸が浅く早くなりがちです。すると交感神経が活発になり、動悸がさらに強くなる恐れがあります。
そこでおすすめなのが「腹式呼吸」です。
ゆっくり鼻から息を吸い、おなかをふくらませたあと、口から細く長く息を吐き切る。このサイクルを数回繰り返すだけでも自律神経が安定しやすくなり、動悸が落ち着く感覚を得やすいでしょう。
呼吸と同時に、姿勢にも意識を向けてください。
デスクワークが長い人は猫背や肩こりなどが進行し、胸を圧迫して呼吸しにくい姿勢になりがちです。肩を軽く回したり背筋を伸ばしたりして、筋肉の緊張を和らげるだけでも気持ちが少し落ち着きます。
クイックストレッチで筋肉をほぐす
動悸と同時に肩や首のこりを自覚する方が多いのは、ストレスや緊張時に筋肉が硬直するからです。そこで、机周りや椅子に座ったままでもできる簡単なストレッチを試してみましょう。
首回りストレッチ
ゆっくり首を左右に回し、痛みのない範囲で前後に倒す。余裕があれば、斜め前や斜め後ろにも首を倒し、凝り固まった筋肉をほぐします。
肩甲骨ストレッチ
両肩をすくめるようにして上に上げ、そのままストンと下ろす。これを数回繰り返した後、肩甲骨を寄せるようにして胸を開きます。呼吸も深く取り込みやすくなり、動悸の緩和に役立ちます。
水分補給と軽いウォーキング
ストレスを感じると、喉が渇いていても気づきにくかったり、飲み物を取るのが面倒になったりしがちです。実は、軽い脱水状態も動悸を強める要因のひとつ。水やお茶などをこまめに摂取し、体内の水分バランスを整えましょう。
また、可能であれば数分だけでも外を歩くなど、軽いウォーキングを取り入れると効果的です。少し外の空気を吸うだけでもリフレッシュになり、交感神経の興奮を抑えて心拍数を安定させるきっかけになります。
メンタルを落ち着かせる簡易テクニック
動悸が起こると「このまま収まらなかったらどうしよう…」と不安が増幅し、余計に苦しく感じる場合が少なくありません。
そこで「グラウンディング」という簡易的なメンタルテクニックを活用してみましょう。
足裏の感覚に意識を集中し、地面にしっかりと両足をつけて、自分の体重を感じ取るようにします。
これだけでも意識が「不安」から「身体の感覚」に移り、頭の中の混乱が少しずつ収まりやすくなります。
香りや音楽によるリラックス効果
対処法としては補助的な手段ですが、アロマやお気に入りの音楽を活用するのも有効です。
香りや音楽は自律神経に働きかけ、心を落ち着かせる手伝いをしてくれます。
可能であればリラックス効果のあるとされるラベンダーや柑橘系の香りを室内に取り入れる、あるいは落ち着いたテンポの音楽をイヤホンで聴くなど、自分が心地よいと感じる環境をつくるのがおすすめです。
2. 原因

ストレスによる動悸には、さまざまな要因が複合的に関わっています。ここでは主な原因を整理し、自分自身の生活習慣や思考パターンを見直すきっかけにしてみてください。
自律神経の乱れ
人間の身体には、交感神経と副交感神経という二つの自律神経が存在します。
ストレスを受けると交感神経が優位になり、心拍数が上がったり呼吸が浅くなったりすることで動悸を感じやすくなります。
慢性的にストレスを抱えていると、このバランスが崩れてしまい、ちょっとしたきっかけでも動悸が起こるようになるのです。
睡眠不足や不規則な生活
睡眠不足や夜更かしなどの不規則な生活リズムは、自律神経の働きをさらに乱します。
特にデスクワークが長時間に及ぶ人は、身体を動かす機会が少ないために血行が悪くなり、疲労が回復しづらい状態になります。
こうした状況が続くとストレス耐性が下がり、小さなストレスでも動悸が出やすくなるでしょう。
カフェインやアルコールの過剰摂取
コーヒーやエナジードリンク、アルコールなどを過度に摂取すると、神経系が刺激されて心拍数が上昇しやすくなります。
特に忙しい時期に「眠気を飛ばすため」「リフレッシュのため」といってカフェインを取りすぎたり、夜にアルコールでストレス発散をしすぎたりすると、かえって睡眠の質が低下し、動悸を感じやすい身体をつくってしまうのです。
思考パターンによる不安増幅
ストレスを受けたときに「また動悸が起こるかもしれない」「一度起きたら止まらないのではないか」と考える思考パターンがあると、不安が不安を呼んで心拍数のコントロールがさらに難しくなります。
これは「予期不安」の一種と呼ばれ、症状を長引かせる原因になることも少なくありません。
運動不足や体力低下
運動不足により体力が低下すると、少し体を動かしただけでも動悸がするようになります。
ここにストレスが加わると、さらに疲労感や緊張感が増し、自律神経も乱れやすくなるという悪循環が起こります。
特にデスクワーク中心の方は座りっぱなしが続くため、気づかないうちに体力や筋力が落ちやすい点に注意が必要です。
3. 予防

「動悸が起こってから対処」するだけでなく、「そもそも動悸が起こりにくい身体や心をつくる」ことが理想です。ここでは日常生活に取り入れられる予防策について詳しく見ていきましょう。
定期的なストレッチ習慣
ストレッチは筋肉をほぐすだけでなく、血行を促進し、呼吸を深める効果も期待できます。
特に寝る前や起床後、デスクワークの合間などに、全身をほどよく伸ばすストレッチを習慣づけることで、身体の緊張をリセットしやすくなります。
また、ストレッチを行うときには反動をつけず、ゆっくりと筋肉を伸ばすように意識しましょう。
十分な睡眠とリラックスタイム
睡眠は自律神経のバランスを整えるうえで欠かせない要素です。就寝前にスマホやパソコンを見続けていると、脳が刺激されて眠りが浅くなりがちです。
ブルーライトを避けるために、就寝30分前からは画面を見るのを控えたり、寝室の照明を落としてリラックスできる空間をつくったりするのがおすすめです。
さらに音楽やアロマなど自分が落ち着く要素を取り入れて、心身をリセットする時間を意識的に確保するとよいでしょう。
食生活の見直し
動悸の予防にはバランスのとれた食生活も大切です。
カフェインやアルコール、糖質の過剰摂取を控え、野菜やタンパク質、良質な脂質をバランスよく取り入れることを意識してみてください。
特に疲労回復やストレス耐性を高めるため、ビタミンB群やマグネシウム、鉄分などのミネラルを豊富に含む食材を積極的に摂るのもポイントです。
軽い運動の習慣化
ウォーキングやスロージョギング、ヨガなど、日常的にできる軽めの運動は自律神経を整え、心肺機能を高める効果があります。
また、運動をすることでストレス解消にもつながりやすく、寝つきやすい身体づくりにもプラスです。
ポイントは「きつすぎない運動」を「続ける」ことであり、ハードなトレーニングを短期間だけ行うよりも、軽めでも長期的な継続が効果を発揮します。
メンタルトレーニングやストレスマネジメント
予防の段階からメンタル面のケアをしておくと、実際にストレスがかかっても動悸が起こりにくくなります。
たとえば、定期的に「自分が感じているストレスを書き出す」「良かったことや感謝できることを日記にまとめる」などの方法を取り入れてみると、自分の状態を客観的に把握しやすくなります。
必要に応じて、カウンセリングやセルフヘルプの書籍なども活用してみるとよいでしょう。
4. 継続するためのコツ

予防策や対処法を知っていても、忙しい日常の中で継続するのは容易ではありません。
ここでは「継続」をキーワードに、ストレスで動悸しがちな方が長期的に心身のコンディションを整えるうえでのポイントを紹介します。
目標を細分化してハードルを下げる
たとえば「毎朝30分ジョギングする」という目標は、高いモチベーションがあるうちは続きますが、忙しくなったり気分が乗らなかったりすると挫折しがちです。
そこで「起きてすぐ5分だけストレッチをする」「帰宅後、靴を履き替えて近所を1周する」など、より小さな習慣から始めると続けやすくなります。
タイマーやアプリを活用する
人間は放っておくと、どうしても「めんどくさい」という気持ちや他の優先事項に流されがちです。
そこでスマートフォンのリマインダーやタイマー機能、運動管理アプリを活用すると、行動のきっかけを作りやすくなります。
「1時間ごとにストレッチの通知が来る」「寝る前に腹式呼吸を促すアラームを設定する」など、自分が取り組みやすいスタイルを探してみましょう。
周囲に宣言して巻き込む
一人で黙々と続けるよりも、家族や友人、同僚など周囲に「最近、ストレスで動悸があるから、ストレッチを習慣化しようと思う」と伝えてみてください。
応援してもらえたり、一緒に取り組む仲間が増えたりすることで、やる気を維持しやすくなります。職場であれば休憩時間に軽いストレッチを提案してみるのもよいでしょう。
ストレッチの質を向上させる工夫
慣れてくるとストレッチを「こなすだけ」になりがちで、効果が出にくくなることもあります。
呼吸をしっかり意識して、伸ばしている筋肉に意識を向けるだけでも質が変わります。
さらに可能であれば週に一度でもいいので、専門家の指導を受けてフォームや負荷をチェックしてもらうと、より確実に効果を得やすくなるでしょう。
自己肯定感を高める
ストレスで動悸を感じる方は、自分の心身の不調を「自分の弱さ」ととらえてしまいがちです。
変化が遅いと「やっぱり自分には無理」「続けても意味がない」とネガティブ思考に陥る場合もあります。
しかし、ちょっとずつでも続けていけば、徐々に身体の反応が変わっていくものです。小さな成功体験を見逃さず、「昨日より息がしやすい」「動悸がおさまるまでの時間が短くなった」などと気づいていくことが、長期的な継続へのエネルギーになります。
5. どうしても解決できない場合は早めに専門家へ相談

対処法や予防策を試してみても改善しない、あるいは動悸の頻度や強さが増していると感じる場合は、早めに専門家へ相談することが大切です。
放置しているとさらに不安が高まり、日常生活に大きな支障が出てしまう可能性があります。
医療機関での診断を受ける
まずは医師の診断を受け、心臓や甲状腺といった臓器に問題がないかどうかを確認することが重要です。
動悸の原因がストレスだけではない可能性もあるからです。
必要に応じて内科や循環器科を受診し、検査を受けて身体的な問題がないかをしっかり把握しましょう。
医師が状況を見極めて、投薬や生活習慣の指導などを提案してくれる場合もあります。
整体で身体のバランスを整える
身体の歪みや筋肉の過度な緊張が、血流や呼吸に影響を与え、動悸を感じやすくしているケースも考えられます。
整体では骨格や筋肉のバランスを調整し、全身の血行を改善することで自律神経を整える効果が期待できます。
ただし、整体院の施術は医療行為とは異なるため、医師による診断と合わせて考えるとより安心です。口コミや評判を調べて、信頼できる施術者を探すのがよいでしょう。
ストレッチ専門家の指導を受ける
自分でストレッチを続けてもなかなか効果を感じられない場合、ストレッチの専門家やパーソナルトレーナーに相談してみるのも手です。
プロの目線で姿勢や筋肉の使い方をチェックしてもらえるため、誤ったフォームや力の入れ方の癖を修正することができます。
結果的に動悸の根本的な原因である筋緊張や呼吸の浅さが改善される可能性が高まるでしょう。
まとめ

対処法
動悸が起こったときは、深呼吸やクイックストレッチで身体の緊張をほぐし、メンタル面ではグラウンディングや音楽・アロマを活用してリラックスを促す。
原因
自律神経の乱れや睡眠不足、カフェイン過多などの生活習慣が重なると動悸を起こしやすい状態に。思考パターンによる不安増幅も原因のひとつ。
予防
日常的なストレッチや軽い運動、十分な睡眠と栄養バランスの整った食事などで自律神経を安定させ、動悸が起こりにくい心身をつくる。
継続するためのコツ
目標を細分化し、タイマーやアプリなどを活用。周囲を巻き込んでモチベーションを維持しながら、小さな変化や成功体験を積み重ねる。
どうしても解決できない場合は早めに専門家へ相談
医療機関で診断を受け、必要があれば整体やストレッチ専門家の指導を検討。早めの対策で不安を減らし、より快適な生活を送れるようにする。
ストレスで動悸が生じると、心も身体も落ち着かなくなり、生産性にも大きく影響します。
しかし、正しい対処法と予防策を知り、それを日常で継続していけば、落ち着きを取り戻すことは十分可能です。
一歩ずつでいいので、自分に合った方法を試し、必要に応じて専門家の力を借りながら、より健康的で充実した毎日を目指してみてください。
参考文献
- 厚生労働省. 食品に含まれるカフェインの過剰摂取についてQ&A
- World Health Organization. Doing What Matters in Times of Stress: An Illustrated Guide
- Ma X, Yue Z-Q, Gong Z-Q, et al. The Effect of Diaphragmatic Breathing on Attention, Negative Affect and Stress. Frontiers in Psychology. 2017;8:874.
- 日本循環器学会. 2. 不整脈の症状は?
- 日本睡眠学会. 睡眠障害対処 12の指針