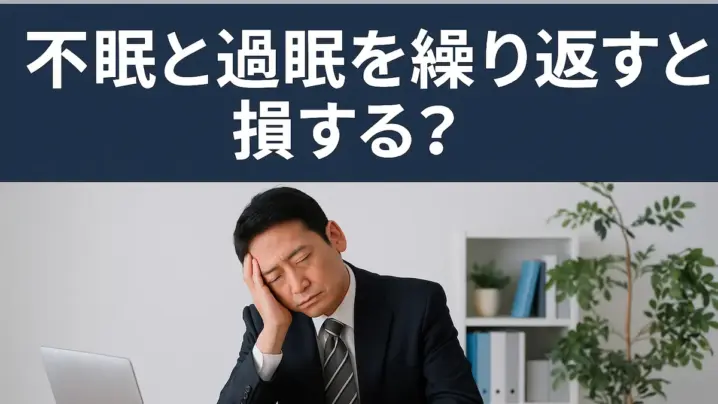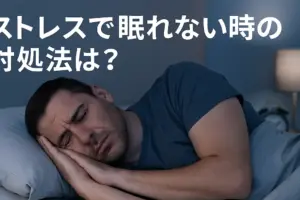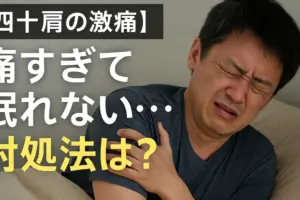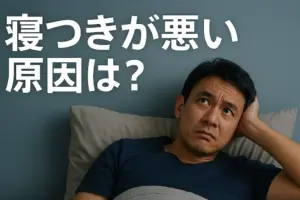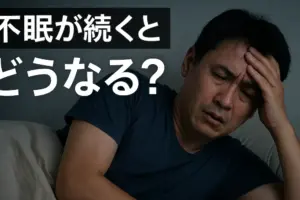最近、夜しっかり眠れないかと思えば、逆に昼間に寝過ぎてしまうことが続いていませんか?
結論をいうと、「不眠と過眠を繰り返す」と損するため、早めに対処することで生活の質を大きく向上できます。
実は…ちょっとしたストレッチ習慣の見直しや生活習慣の調整で改善が期待できるケースも多いのです。
この記事では、ストレッチの専門家が対処法から予防策まで詳しく解説します。
…………………………………………………………
目次(Contents)
1. 対処法

まずは自分の状態を把握する
「不眠と過眠を繰り返す」状態とは、夜に思うように寝つけない日と、日中に耐えられないほどの眠気を感じて長時間寝てしまう日が交互にやってくることを指します。
デスクワーカーの方であれば、昼に意識がもうろうとして作業効率が落ちたり、逆に夜になると目が冴えて睡眠不足が重なるなど、生産性に大きく影響が出ます。
自分の生活リズムを記録してみる
まずは1〜2週間程度、睡眠と起床の時間、日中の眠気の強さ、食事の時間や内容などを簡単に記録してみるとよいでしょう。
スマートフォンのメモや睡眠計測アプリなど、便利なツールがいくつもあるので活用すると管理が楽です。
自分の睡眠パターンを客観的に把握すると、どのタイミングで不眠になりやすいのか、あるいは過眠になりやすいのかがわかりやすくなります。
ストレッチによるリラックス効果を活かす
「不眠と過眠を繰り返す」状態を改善する上で、身体をほぐしてリラックス状態をつくるストレッチは非常に効果的です。
特に夜、寝る前に軽いストレッチを習慣化することで、自律神経のバランスを整え、入眠しやすい状態をつくりやすくなります。
1. 首回りのストレッチ
• ゆっくりと首を前後左右に倒す
• 回数はそれぞれ5〜10回ずつ、反動をつけずに行う
• デスクワークで固まりやすい首周辺をほぐす
2. 肩甲骨まわりのストレッチ
• 両手を肩に置き、肘で大きな円を描くように回す
• 前回し・後ろ回しそれぞれ5〜10回
• 血行促進を促し、上半身の緊張を和らげる
3. 股関節のストレッチ
• 床に座って、足の裏同士を合わせて両手でつかみ、膝をゆっくり上下させる
• 股関節まわりをほぐすことで下半身の血流をスムーズに
デスクワークの方はとくに肩や首、背中のコリが強くなりやすいので、布団に入る前にこれらのストレッチを1セット取り入れるだけでもリラックス効果が期待できます。
光と温度を意識した睡眠環境づくり
夜にしっかり眠るためには、部屋の明るさと室温・湿度管理が重要です。特に光の刺激は自律神経やホルモン分泌に大きく影響します。
就寝前はスマホやパソコンの画面から離れる
ブルーライトは脳を覚醒させる働きがあるため、寝る直前まで画面を見続けると、入眠を妨げやすくなります。
最低でも就寝30分前にはスマホやパソコンから離れる意識を持ちましょう。
適切な室温・湿度を保つ
夏場は27〜28℃前後、冬場は18〜20℃前後を目安に。湿度は50〜60%程度が快適といわれています。
エアコンや加湿器、除湿機などを使ってできるだけ過ごしやすい環境を整えましょう。
一時的に仮眠(ナップ)を取り入れる
日中にどうしても強烈な眠気に襲われ、仕事のパフォーマンスが落ちてしまう場合は、一時的な仮眠の活用が有効です。
ただし、仮眠の長さやタイミングを誤ると夜の不眠がさらに悪化する恐れがあるので注意しましょう。
最適な仮眠時間は20分程度
30分以上寝てしまうと深い眠りに入り、起床後の倦怠感や夜の睡眠リズムの乱れにつながりやすいとされています。
昼過ぎまでに抑える
昼食後から14時〜15時頃までに20分程度の仮眠をとると、脳をリフレッシュさせ、午後の作業効率を高められます。
逆に夕方以降に仮眠をすると夜の入眠を妨げる原因になることがあるので避けたほうが無難です。
こうした工夫を取り入れることで、夜の睡眠と日中の仮眠をうまくバランスさせられるようになるでしょう。
2. 原因

生活リズムの乱れ
「不眠と過眠を繰り返す」状態の根本原因の一つに、生活リズムの乱れが挙げられます。
デスクワーカーの多くは朝から夕方までほぼ座りっぱなしで仕事をすることが多く、運動不足や長時間のパソコン・スマホ利用による刺激過多が起こります。
昼夜逆転に近いスケジュール
夜遅くまで作業やSNSのチェックを行い、翌朝ぎりぎりに起きる生活を続けていると、体内時計がずれてしまう原因に。
運動不足で体力が余ってしまう
身体を動かさないと筋肉の疲労が少なく、なかなか寝付けなくなる場合があります。
とくに日常的に運動しない人や、通勤が車中心で歩く機会が少ない人は要注意です。
ストレスや精神的負担
ストレスもまた、不眠と過眠の反復を引き起こす大きな要因です。
仕事でのプレッシャーや人間関係の悩みがあると、夜に考え事が止まらず入眠できないことが増え、結果として睡眠不足が続きます。
するとある日、疲れが限界に達して長時間寝てしまう、というサイクルに陥りやすくなるのです。
不安や緊張から交感神経が高ぶる
就寝前までストレスを感じていると心拍数が上がったままで、リラックスモードに移行しにくくなります。
休日に寝溜めしようとする
平日の睡眠不足を休日にまとめて補おうとして大量に寝てしまうと、かえって体内リズムが乱れることがあります。
栄養バランスや食事のタイミング
食事の内容が極端に偏ったり、就寝直前に満腹になるような食事を摂ると、身体が消化活動で活発に働くため、寝つきが悪くなる場合があります。
一方で過度なダイエットなどで栄養が不足すると、身体機能のバランスが崩れ、睡眠の質自体が低下することも。
カフェインやアルコールの影響
コーヒーや緑茶などに含まれるカフェインは覚醒作用があるため、就寝前に摂取すると不眠に陥りやすいです。
またアルコールは一見眠気を誘うように感じますが、利尿作用や睡眠サイクルの乱れを起こす要因にもなります。
空腹でも眠りにくい
お腹が空きすぎる状態だと身体がエネルギー補給を求めて眠りを妨げることがあります。
寝る前の軽いトーストや牛乳など、消化に負担をかけない軽食をとることで眠りやすくなる場合もあります。
自律神経の乱れ
不規則な生活やストレス、運動不足などの要因が重なると、自律神経がアンバランスになりやすくなります。
自律神経は交感神経と副交感神経によって成り立っており、正常ならば昼間は活動モード(交感神経優位)、夜は休息モード(副交感神経優位)に自然と切り替わります。
しかし、なんらかの理由でこの切り替えがスムーズにいかないと、不眠→過眠→不眠…の悪循環に陥るのです。
夜なのに交感神経が高ぶり続ける
脳が“昼”と勘違いしているような状態。寝ようと思っても頭が冴えて眠れない。
日中に副交感神経が強く働いてしまう
休息モードが昼間にやってきてしまい、強い眠気に襲われる。
こうした自律神経のトラブルはストレッチや適度な運動を通じて改善が見込めますが、場合によっては専門家の力を借りることも必要になってくるでしょう。
3. 予防

睡眠スケジュールの固定
毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きるよう意識することが、最も基本的で効果的な予防策といえます。
たとえば朝7時に起きると決めたら、休日であっても8時や9時まで寝ないように工夫しましょう。
夜はできれば23時~0時までには就寝するのが理想ですが、仕事の都合で難しい方は「寝る時間」と「起きる時間」の幅をできる限り一定に保ちましょう。
適度な運動習慣
健康への投資意識が高い方こそ、日々の運動を習慣化すると睡眠の質の向上やストレス発散に大きく寄与します。
ジム通いがハードルが高い場合でも、ウォーキングや階段の利用、軽いジョギングなどで身体を動かす機会を増やすだけでも変化を感じやすいものです。
• ランチタイムウォーキング
お昼休みの時間を活用して10〜15分だけでも散歩をすることで、座りっぱなしの生活を少しでも改善し、体内リズムを整えるのに役立ちます。
• 仕事帰りにひと駅歩く
帰宅の途中で一駅分歩くなど、無理のない範囲で続けられる習慣づくりがポイントです。
ストレスコントロール
ストレスが蓄積すると、どうしても夜の寝つきや睡眠の質に影響が出ます。
デスクワークで長時間集中が必要な方ほど、意識的なリフレッシュが大切です。
• 短時間でも良いので趣味やリラックスタイムを確保
好きな音楽を聴いたり、読書や軽いストレッチ、ヨガなどを通じて心身を解放する時間を作りましょう。
• 呼吸法を意識する
深呼吸を意識して副交感神経を優位にすることで、緊張状態から脱しやすくなります。
寝る前に数分間のゆったりした呼吸法を試してみると、入眠をサポートしてくれます。
栄養バランスの整った食生活
主食、主菜、副菜をバランスよく摂取し、ビタミンやミネラルもしっかり補うことで、身体が必要とするエネルギーと栄養素をきちんとカバーできるようにしましょう。
• 朝食をとる習慣
体内リズムを整える上で朝食は重要です。食事をとることで“朝が来た”と身体に信号を送り、スムーズな1日のスタートを促します。
• カフェインの摂取タイミングを調整
どうしてもコーヒーが好きでやめられない場合は、午前中や昼過ぎまでに限るなど、摂取する時間帯を意識して睡眠の妨げを減らしましょう。
4. 継続するためのコツ

一度に変えすぎない
「不眠と過眠を繰り返す」状態から抜け出すためには、生活習慣を見直す必要があるものの、一度に多くのことを変えようとすると挫折しやすくなります。たとえば、
• 夜のストレッチを1セットから始める
• まずは寝る時間だけ毎日固定する
• 週に一度、軽い運動を取り入れる
といったように、できる範囲で徐々に取り組んでいく方が成功しやすいです。
習慣化をサポートする工夫
忙しいデスクワークの合間に継続していくには、仕組みづくりが大切です。
• スマホのアラームやリマインダーを活用
就寝30分前にスマホの通知を設定し、「そろそろ画面を見ない時間を作る」きっかけにする。
• 家族や同僚、友人に宣言する
自分が取り組んでいる習慣を周囲に知らせることで、サポートを得やすくなるほか、モチベーションも維持しやすくなります。
小さな成功体験を積む
人間は「昨日より少し楽に寝付けた」「朝の目覚めがちょっと良かった」というポジティブな変化があると、次も続けようという気持ちが強くなります。
不眠と過眠を繰り返す中でも、小さな前進を記録して自分を肯定することが大切です。
• 日々の睡眠ログで変化を見える化
「昨夜は寝る前のストレッチでリラックスできた」「今日は昼間の眠気が軽かった」など簡単にメモしておく。
5. どうしても解決できない場合は早めに専門家へ相談

医療機関への相談
「不眠と過眠を繰り返す」問題が長期化し、日常生活や仕事に大きな支障をきたしている場合は、迷わず医療機関を受診しましょう。
内科や精神科、心療内科など、睡眠障害に対応しているクリニックであれば、原因を客観的に調べて、必要に応じた薬物療法やカウンセリングを提案してくれます。
• 睡眠の専門外来があるか確認
病院やクリニックによっては睡眠障害専門の外来を設けているところもあります。
整体やストレッチ専門の施設
運動不足や身体の歪みが原因で自律神経が乱れているケースも少なくありません。
整体やストレッチ専門の施設では、身体の使い方の癖をチェックしてもらいながら、筋肉バランスを整えるサポートが受けられます。
• メンテナンス感覚で通いやすい
「めんどくさい」ケアをまとめてプロに任せたい、という方にとっても、整体やストレッチ施設は魅力的な選択肢です。忙しい方こそ短時間でも定期的にプロに身体をほぐしてもらうだけで、疲労感が軽減するケースは少なくありません。
自己判断をしすぎない
不眠や過眠の原因には、ストレスや生活習慣だけでなく、まれに別の疾患が隠れていることもあります。
素人判断で「まあ大丈夫だろう」と放置していると、状態が悪化する可能性も。早めに専門家に相談することで、根本的な原因を特定し、より適切なアプローチをとれる確率が高まります。
まとめ

対処法
夜の入眠を助けるストレッチや昼間の仮眠(20分程度)の活用、睡眠環境を整えることが重要。
特に就寝前のスマホ利用を減らし、光刺激をコントロールすると質の良い睡眠がとりやすくなる。
原因
生活リズムの乱れやストレス、栄養バランスの偏り、自律神経の乱れなど、多角的な要因が絡み合っている。
夜更かしや休日の寝溜め、精神的負担の蓄積により不眠と過眠が繰り返されるケースが多い。
予防
一定の睡眠スケジュールを守り、適度な運動習慣やバランスの良い食事を心掛ける。
デスクワーカーはできるだけ身体を動かす機会を増やし、ストレスを適切にコントロールして自律神経を整えることが有効。
継続するためのコツ
一気にすべてを変えようとせず、小さなステップから始める。
習慣化しやすい仕組み(スマホのリマインダーや周囲への宣言など)を活用し、小さな成功体験を積み重ねることで継続を後押しする。
どうしても解決できない場合は早めに専門家へ相談
長引く場合や症状が深刻な場合は医療機関で検査を受ける。
整体やストレッチ専門施設で身体の歪みを整えてもらうのも効果的。自己判断で放置せず、専門家に任せることで的確なアプローチをとれる。
結局のところ、「不眠と過眠を繰り返す」状態を解消し、生産性の高い毎日を送るためには、生活習慣の見直しとストレッチなどのケアをバランスよく取り入れることが鍵です。
デスクワーカーをはじめとする忙しい現代人だからこそ、定期的な身体のメンテナンスや時間管理が重要になってきます。
小さな変化の積み重ねが大きな成果を生むことを意識し、できる範囲から始めてみましょう。
参考文献
- 厚生労働省 e-ヘルスネット. 不眠症(症状・原因・対処の基礎知識)
- 日本睡眠学会. ガイドライン・声明(不眠・過眠関連の診療指針等)
- World Health Organization. Q&A: Stress(睡眠衛生の実践:就寝前の端末・飲食・運動など)
- Edinger JD, et al. Behavioral and psychological treatments for chronic insomnia disorder in adults: Clinical practice guideline(2021, J Clin Sleep Med)
- American Academy of Sleep Medicine. Excessive daytime sleepinessに対する新ガイドラインの臨床推奨(2025)