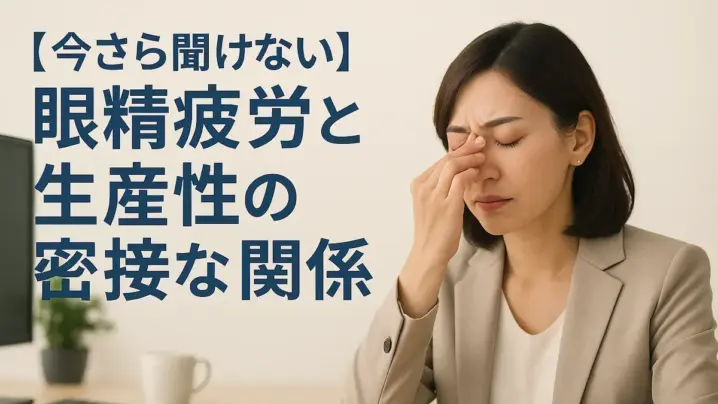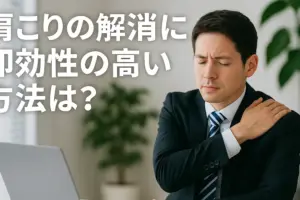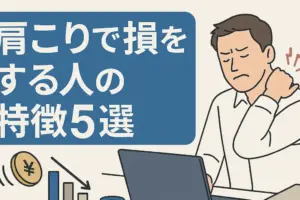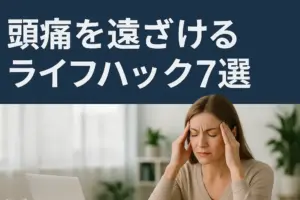「目の奥がズーンと重い…画面が霞んで仕事に集中できない」そんな経験はありませんか?
結論をいうと、眼精疲労は生産性著しく下げます。
実は…目の疲れは集中力と判断力を奪い、仕事の質に直結します。
この記事では、ストレッチの専門家が眼精疲労と生産性の関係を徹底解説します。
………………………………………………………….
目次(Contents)
1. 眼精疲労とは?症状とメカニズム
 眼精疲労とは、目を酷使したあとに「休憩を取っても十分に回復しない持続的な疲れ」のことを指します。一般的な“目の疲れ”と異なり、しばしば全身症状を伴うのが特徴と言われています。たとえば次のようなサインがあれば要注意です。
眼精疲労とは、目を酷使したあとに「休憩を取っても十分に回復しない持続的な疲れ」のことを指します。一般的な“目の疲れ”と異なり、しばしば全身症状を伴うのが特徴と言われています。たとえば次のようなサインがあれば要注意です。
- 目の奥やこめかみがジーンと痛む
- ピントが合わず、文字が二重に見える
- まぶたが重く開けているのがつらい
- 肩こりや首こり、頭痛が一緒に起きる
- 夜になるとやる気が極端に落ちる
これらは「目だけの問題」に留まらず、自律神経の乱れによって全身の血流が悪化し、慢性的な倦怠感や睡眠の質低下にも波及するとされています。
メカニズムは“焦点調節”と“瞬目”の乱れ
人が画面を見続けると、水晶体の厚みを変えてピントを合わせる毛様体筋が緊張しっぱなしになります。筋肉が収縮し続けると血流が滞り、乳酸などの代謝産物が蓄積。これがいわゆる“だるさ”や“痛み”の正体です。また、集中していると瞬きを忘れがちになり、角膜を守る涙が蒸発。ドライアイ状態になって角膜が微細な炎症を起こし、刺激がさらに疲れを増幅する悪循環に陥るといわれます。
眼精疲労が全身に波及する理由
目から入る情報は視神経を通じて脳へダイレクトに届きます。視覚は五感の中でも処理負荷が大きく、脳は全エネルギーの約2割を消費すると言われています。目が疲れると脳も過労状態になり、交感神経が優位に傾いて筋緊張を高めます。その結果、肩や首がガチガチに固まり血流がさらに悪化——いわば“負のスパイラル”が完成します。こうした生理学的背景があるため、単なる目薬や休憩だけでは根本解決が難しいのです。
デスクワーカーが陥りやすい3つの落とし穴
- 長時間の近接作業 ノートPCを膝に乗せたり、スマホを顔の近くで操作する癖があると、焦点調節筋は常に限界域で働き続けます。
- 照度とコントラストのアンバランス オフィス照明は500lx程度が一般的と言われていますが、外光を背にするとディスプレイが眩しく、瞳孔がチカチカと開閉を繰り返し疲労を招きます。
- 無意識の猫背姿勢 画面に顔を近づけるクセは頭部の重さを支える僧帽筋や胸鎖乳突筋に過負荷をかけ、首・肩こり→血流悪化→眼精疲労というループを引き起こします。
仕事終わりに感じる「脳のもやもや」
集中が切れてミスが増える、会議でアイデアが出てこない——これも眼精疲労のサインと指摘されています。脳は視覚情報の処理にリソースを奪われると、論理思考や創造性に割ける余力が減少。“頭が回らない”と感じるのは単なる疲れではなく、視覚過多によるリソース枯渇に他なりません。
2. なぜ生産性が落ちるのか?眼精疲労が仕事の質に与える影響
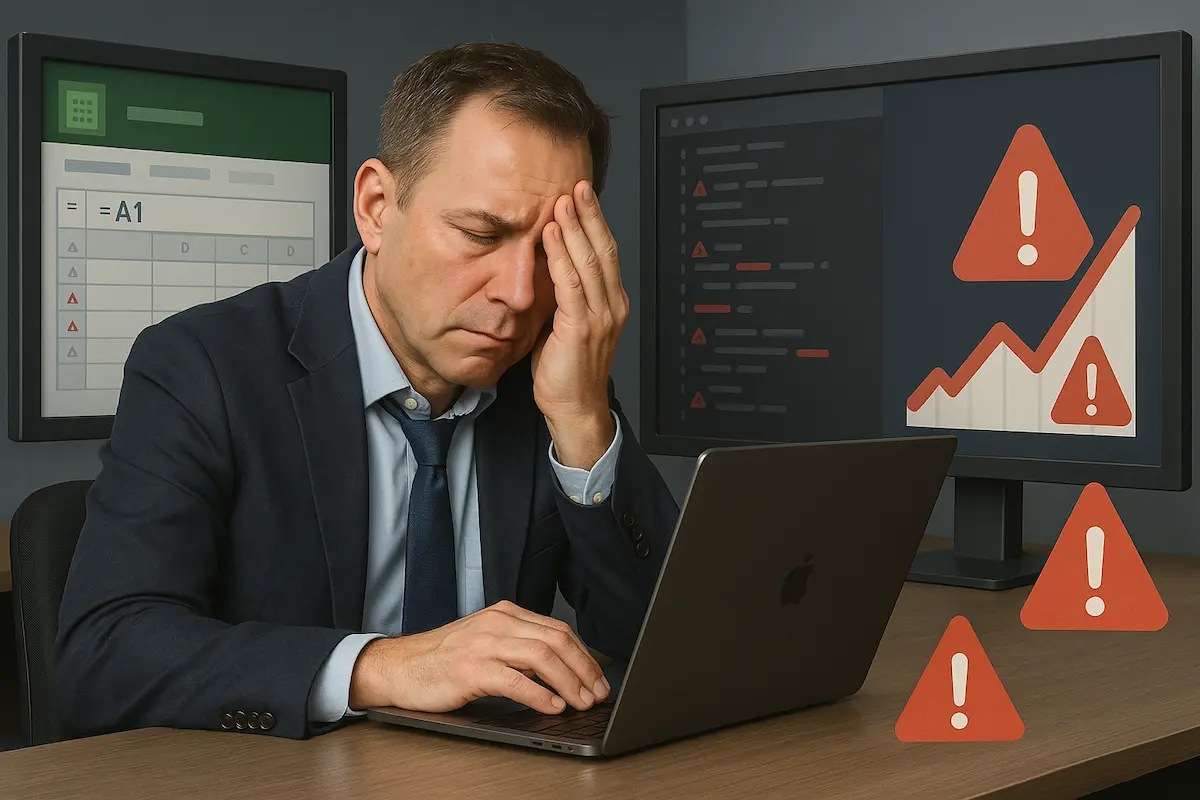 「目が疲れているだけで、アウトプットは変わらない」と感じるかもしれません。しかし実際には、眼精疲労は次の3つの側面で生産性を大幅に下げるとされています。
「目が疲れているだけで、アウトプットは変わらない」と感じるかもしれません。しかし実際には、眼精疲労は次の3つの側面で生産性を大幅に下げるとされています。
① 集中力の持続時間を短縮する
人間の集中には“覚醒レベル”と“作業興奮”という二段階があります。目がしょぼつき始めると、まず覚醒レベルが低下し、脳波はリラックス寄りのアルファ帯域へ移行。さらに視覚情報の処理にエネルギーを消耗するため、作業興奮が高まらず“やる気スイッチ”が入らない状態になります。結果として、一度に取り組める時間が30分→10分→5分と短縮し、タスク切り替えのロスタイムが増大。細切れ作業が連続すると心理的な達成感も薄れ、自己効力感の低下へつながると言われます。
② 判断ミス・誤入力の増加
ディスプレイ上の文字がぼやけると、脳は“補完”によって情報を推測します。この作業は通常よりも高いエネルギーを要するため、疲労した脳は推測精度が下がり、誤字や数値入力ミスを引き起こします。特にExcelの数式チェックやコードレビューのような視覚精度が求められる作業では、1日の終盤にエラー率が急上昇する可能性が非常に高いです。「夕方になるとケアレスミスが増える」という声の裏には、眼精疲労による視覚的ノイズが潜むと言えるでしょう。
③ 創造性の低下とストレス増幅
目は脳を直接刺激する“外部センサー”であり、視覚負荷が高いと創造系ネットワーク(デフォルトモードネットワーク)の活動が鈍るとも示唆されています。アイデアを出す会議で“頭の中が真っ白”になるのは、眼精疲労によって脳の余剰資源が少なくなっている証拠。さらに、目の痛みや乾燥は交感神経を刺激しやすく、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌を高めるとされています。ストレスフルな状態ではクリエイティブ思考どころか、人間関係の摩擦も起こりやすくなる——眼精疲労は個人だけでなく、チーム全体のパフォーマンスにも影響を及ぼすのです。
見落とされがちな「生産性の質」への打撃
生産性を「こなしたタスク量」で測るだけでは不十分です。質の高いアウトプットを出すには、情報を統合し、新しい視点を生み出す“高次認知”が欠かせません。視覚疲労がピークに達すると、脳は入ってきた情報をただ処理するだけで精一杯になり、洞察や判断のクオリティが急激に低下すると指摘されています。つまり、眼精疲労は定量的な生産性(タスク量)と定性的な生産性(アウトプットの質)の両面に打撃を与える“隠れコスト”なのです。
眼精疲労を甘く見ると組織全体で月⚪︎時間の損失に?
国内外の調査では、「集中力が切れたことによる再集中のやり直し」に1日あたり平均45分程度を費やしているという推計があります。全社員が同じ状況に陥れば、月間で換算すると膨大な作業ロスが発生する計算です。つまり、眼精疲労対策は個人の健康問題にとどまらず、組織の経営課題としても無視できないテーマと言えるでしょう。
3. デスクワーカーに多い原因とセルフチェック
 多くのデスクワーカーが眼精疲労に悩むのは、作業環境と生活習慣に“疲れを生む仕掛け”が潜んでいるからです。ここでは代表的な4つの原因を深掘りし、ご自身がどれに当てはまるかセルフチェックしてみましょう。
多くのデスクワーカーが眼精疲労に悩むのは、作業環境と生活習慣に“疲れを生む仕掛け”が潜んでいるからです。ここでは代表的な4つの原因を深掘りし、ご自身がどれに当てはまるかセルフチェックしてみましょう。
1) ディスプレイとの距離・高さのミスマッチ
- 距離 一般に、画面までの距離は「モニター対角の約1.5倍」が目安と言われます。ノートPCを顔の近くで使うと焦点調節筋が常に緊張し、10分ほどで眼圧が上昇するケースも。
- 高さ 視線が水平より10度ほど下を向く位置が最も負担が少ないとされます。見上げる姿勢はまぶたが開き気味になり、ドライアイを招きやすいのが難点。
セルフチェック: 画面を見ながら首の後ろに手を当て、筋肉が硬く張っていたら要改善サイン。
2) 照明とブルーライト
- 室内照度が明るすぎる場合、瞳孔が絞まり筋肉が緊張。逆に暗すぎると画面とのコントラストが強く、瞬きが減少します。
- 夜間のブルーライトは概日リズムを乱し、寝付きの悪化→翌日の眼精疲労増幅というサイクルを生むとされています。
セルフチェック: 画面の輝度を最小にし、違和感なく読めるなら明るすぎ。暗くして痛むなら暗すぎ。
3) 姿勢と呼吸パターン
猫背やスマホ首で頭が前に出ると、僧帽筋や胸鎖乳突筋が緊張し、首の血流が悪化。これにより酸素と栄養が目に届きにくくなると言われています。また、浅い胸式呼吸が続くと脳への酸素供給も不足しがちです。
セルフチェック: 椅子に深く座り、背もたれに寄りかかって深呼吸したとき胸郭が硬いならNG。
4) 連続作業時間と休憩リズム
「会議と会議の間が5分しかなく、目を休める暇がない」という状況はデスクワーカーあるある。焦点調節筋は20分の連続使用で急激に疲れると言われており、まとまった休憩が取れない環境は眼精疲労を助長します。
セルフチェック: Pomodoroタイマーなどを使い、25分集中→5分休憩を試し、集中の質が上がるかを確認。
5) 水分・栄養不足
目の表面を潤す涙は水分と電解質から構成され、ビタミンAやDHAなどの栄養も欠かせません。カフェイン飲料に偏り水分が不足すると、涙の質が悪化し乾燥を誘発。さらに血糖値の乱高下は視覚のぼやけを招くとされます。
セルフチェック: 午前と午後で1リットルずつ、こまめな水分補給ができているか振り返りましょう。
原因の“掛け算”がリスクを増幅
一つひとつの要因は小さくても、複数が重なると疲労は指数関数的に増えます。たとえば「猫背+低いノートPC+暗い照明」の組み合わせ。原因を可視化し、1つずつ潰すだけでも負担は大幅に軽減すると覚えておきましょう。
4. 今すぐできるセルフケア:眼精疲労対策ストレッチ&エクササイズ
 ここからは、道具いらず・場所いらずで行える“目と全身をつなぐ”ストレッチを紹介します。いずれも1種目30秒〜1分あれば完了。業務の合間に組み込むことで、目のリフレッシュと集中力リセットが同時に狙えます。
ここからは、道具いらず・場所いらずで行える“目と全身をつなぐ”ストレッチを紹介します。いずれも1種目30秒〜1分あれば完了。業務の合間に組み込むことで、目のリフレッシュと集中力リセットが同時に狙えます。
① アイソメトリック視点移動ストレッチ
- 背筋を伸ばして座り、親指を顔の前に立てる。
- 親指を動かさず、眼球だけを右端→左端→上端→下端へゆっくり動かす。各方向5秒キープ。
- 1周したら目を閉じ、深呼吸を3回。3セットが目安。
ポイント: 眼筋と同時に副交感神経が優位になり、眼圧が下がると言われています。ディスプレイを見続けた後のリセットに最適。
② 肩甲骨リリース+胸開き呼吸
- 椅子に浅く腰掛け、両手を肩に添えて肘で大きな円を描く。10回前回し→10回後ろ回し。
- 両手を背もたれの後ろで組み、胸を開いて鼻から深く息を吸う。口からフーッと吐きながら肩を下げる。
- 3呼吸×2セット。
ポイント: 胸郭を開いて酸素摂取量を増やし、脳の覚醒レベルを正常化。血行が促進され、目の代謝もサポートします。
③ 頭部リンパポンピング
- 両手の指先をこめかみに当て、小さな円を描くように30秒マッサージ。
- 耳の後ろ→首筋→鎖骨へ向け、リンパの流れを意識して優しくなで下ろす。
- 最後に両肩をすくめてストンと落とす動作を5回。
ポイント: 老廃物の排出が促されるとともに、脳への血流がクリアになる感覚が得られやすいと言われます。
④ 座ったままハムストリングスストレッチ
- 椅子に浅く座り、片脚を前に伸ばして踵を床につける。
- 骨盤から上体を前傾させて脚裏を伸ばす。30秒キープ。反対側も同様に。
- 2セット。
ポイント: 下肢の血流を改善すると心臓への戻り血量が増え、脳—目—全身への循環が整います。座りっぱなしでむくみがちな方に◎。
⑤ 20-20-20ルール+マイクロブレイク
- 20分作業したら、20フィート(約6m)離れた場所を20秒見る習慣を作る。
- その間に首を左右に倒し、肩をゆっくり回すと効果倍増。
- タイマーアプリを使いルーチン化すると、習慣化のハードルが下がります。
習慣化のコツは“トリガー”を決めること
ストレッチを続けるコツは、日常の行動に結びつける“トリガー”を設置すること。「メールを送ったら」「会議終了後」「14時のコーヒー休憩」など、具体的な行動とセットで決めておくと実践率が高まると言われています。小さなリセットを積み重ねることが、眼精疲労を溜めない最大の秘訣です。
5. 予防と習慣化:仕事と生活に組み込む仕組みづくり
 眼精疲労対策は“イベント”ではなく“習慣”に落とし込むことで真価を発揮します。ここでは、忙しいデスクワーカーでも無理なく継続できる仕組み化テクニックを紹介します。
眼精疲労対策は“イベント”ではなく“習慣”に落とし込むことで真価を発揮します。ここでは、忙しいデスクワーカーでも無理なく継続できる仕組み化テクニックを紹介します。
1) 仕事環境のアップデート
- モニターアーム導入: 画面の高さと距離をワンタッチで調整できるため、姿勢維持が格段に楽になります。
- 外部キーボード&スタンド: ノートPCを目線の高さに上げ、外付けキーボードで手首の負荷を軽減。
- 照明の最適化: デスクライトをディスプレイと対角に配置し、反射を防ぐ。光源の色温度は5000K前後が目安と言われます。
2) デジタルウェルネスアプリの活用
タイマーアプリで20-20-20ルールを自動通知させたり、スマートウォッチで瞬き回数・姿勢の傾きを検知し振動でリマインドさせる仕組みが注目されています。データ可視化によって“気づける化”することで、セルフケアの継続がグッと楽に。
3) 行動トリガーと報酬設計
- トリガー: 「メール送信後」「資料印刷中」「飲み物を取りに行くついで」など毎日のルーチンに“ストレッチ”を紐付ける。
- 報酬: ストレッチを実行できたらお気に入りのプレイリストを1曲聴く、SNSで進捗を報告するなど小さな報酬を設定。
4) オフタイムのリカバリー習慣
- 睡眠の質向上: 就寝1時間前のスマホ断ち、遮光カーテン、深呼吸で副交感神経優位に。
- 栄養リセット: ビタミンB群・ルテイン・アスタキサンチンを含む食材を意識。水分は体重×35mlを目標に。
- アクティブレスト: 休日に軽いジョギングやヨガを取り入れ、全身の代謝を高めると目の疲れも抜けやすいとされています。
5) チームで取り組む「集団効果」
個人努力だけでなく、チーム単位で公式に眼精疲労対策を導入すると遵守率が高まります。たとえば、
- 朝礼で1分間のアイエクササイズ
- 定例会議前に肩甲骨ストレッチ
- 社内チャットで“休憩タイム”をリマインド
といった小さな取り組みを共有することで、“皆でやるから継続しやすい”環境が作れます。
6) KPIを設定しよう
数値化できない習慣は続きにくいものです。次のKPIを設定してみましょう。
- 1日の瞬き回数(目安:1分間に15〜20回)
- 20-20-20ルールの実施回数(目標:勤務時間×2/3)
- 週あたりのストレッチ実施日数(目標:5日以上)
スマートウォッチや無料アプリで測定し、週次で振り返ることでPDCAが回しやすくなります。進捗が可視化されるとモチベーションが維持しやすく、結果として“当たり前の習慣”として定着するでしょう。
継続のコツは“完璧を求めない”こと
やらなかった日は“ゼロ”ではなく“マイナス”と捉えないことが大切です。1日サボっても翌日に2回実践すればプラスマイナスゼロ。眼精疲労対策はマラソンのような長期戦。フレキシブルに続けるマインドセットを持てば、半年後の生産性は確実に変わります。
6. FAQ

Q1. ブルーライトカットメガネは本当に効果がありますか?
A. ブルーライトカットメガネは、短波長光の刺激を和らげることで網膜への負担を軽減するとされています。ただし、カット率が高すぎると色味が変わりデザイン業務などに支障をきたす場合も。目安としてはカット率40%前後のレンズがバランスが良いと言われます。併せて画面輝度を抑え、照明環境を整えることで効果が高まります。
Q2. 目薬だけで眼精疲労は改善できますか?
A. うるおい補給や炎症緩和の点では一定の効果が期待できます。ただし、目薬はあくまで対症療法。焦点調節筋の緊張や姿勢不良といった根本要因を放置していると、痛みや視界のぼやけが再発しやすいです。目薬+ストレッチ+休憩の複合アプローチが推奨されます。
Q3. オフィスで堂々とストレッチするのが恥ずかしいのですが…
A. 視線が気になるのは最初だけという声が多く、習慣化すると同僚も巻き込み“健康文化”が根づくケースが多数報告されています。どうしても抵抗がある場合はトイレ休憩や給湯室など、人の目が少ない場所で1分だけ実践してみるとハードルが下がります。
Q4. コンタクトレンズユーザーは何に気をつけるべき?
A. 装用時間が長いほど角膜が酸欠状態になりやすく、ドライアイ症状が悪化するおそれがあります。外せる環境なら昼休みに外す、難しい場合は高酸素透過性タイプへの変更を検討すると良いでしょう。人工涙液でうるおいを補うのも有効です。
Q5. 休日にまとめて寝れば疲れは取れますか?
A. “寝だめ”は体内時計を乱し、むしろ月曜日の集中力低下を招くと指摘されています。平日も最低6時間半の睡眠を確保し、就寝前のスマホ断ちでメラトニン分泌を促すことが眼精疲労回復の近道です。
Q6. カフェインの摂りすぎは眼精疲労に関係しますか?
A. カフェインは一時的に覚醒度を上げますが、利尿作用で体内の水分・電解質を奪い涙の質を低下させると言われます。1日の摂取量はコーヒー3杯程度(カフェイン300mg前後)を上限とし、同量の水をプラスで補給するのが理想的です。
Q7. PC用モニターとタブレット、目に優しいのはどっち?
A. タブレットは近距離で使用するため焦点調節筋への負担が大きい一方、リフレッシュレートが高くフリッカーが少ない機種も存在します。重要なのは“距離と角度”の確保と“照度設定”の最適化。デスクワークにはPC用モニター+外付けキーボードが推奨されますが、どうしてもタブレットを使う場合はスタンドで高さを合わせ、文字サイズを大きめに設定すると負担軽減につながります。
Q8. 目を温めるのと冷やすの、どちらが良い?
A. スマホやPC使用後の“張り”や“ピントぼやけ”には温めるケアがおすすめです。蒸しタオルで40℃前後に温めると血行が促進され、毛様体筋が緩みピント調節力が回復しやすいと言われます。反対に、炎症や充血を感じる場合は冷却ジェルシートで2〜3分冷やし、血管を収縮させると痛みを抑えやすいです。症状に応じて使い分けると効果的です。
Q9. ショートスリーパーでも目を守る方法はある?
A. 睡眠時間が短くても、質を高めれば回復力はある程度カバーできます。具体的には寝入りばなの90分(深いノンレム睡眠)を確保するため、就寝前のブルーライト遮断と室温18〜20℃の環境づくりが推奨されます。加えて、起床後に朝日を浴びることで体内時計がリセットされ、日中の覚醒レベルが安定しやすいと言われます。
専門家へ相談するときの選択肢
 セルフケアで一定の効果が得られても、「夕方以降の痛みが消えない」「頭痛や吐き気を伴う」といった場合は専門家への相談が不可欠です。ここでは代表的な3つの窓口を整理し、それぞれの特徴と活用ポイントを紹介します。
セルフケアで一定の効果が得られても、「夕方以降の痛みが消えない」「頭痛や吐き気を伴う」といった場合は専門家への相談が不可欠です。ここでは代表的な3つの窓口を整理し、それぞれの特徴と活用ポイントを紹介します。
(1) 医療機関(眼科・脳神経内科)
- 眼科 ドライアイや屈折異常、視力低下など、目そのものに起因する疾患の有無をチェックできます。視力検査や角膜染色などの検査を行い、点眼治療や眼鏡処方を提案されるケースが一般的。
- 脳神経内科 目の痛みと同時に片頭痛やめまいがある場合、神経伝達のトラブルが隠れている可能性も。脳波検査やMRIで器質的疾患の有無を確認し、薬物療法や生活指導を受けられます。
メリット: 病気の早期発見や医学的根拠に基づく治療が可能。
注意点: 予約や検査に時間がかかる場合があり「今すぐ何とかしたい」ニーズにはフィットしにくい。
(2) 整体ストレッチ
整体ストレッチは「整体のアジャスト技術」と「パートナーストレッチの深層筋を伸ばす技術」のいいとこ取りであると言われています。施術者が体全体を整えながら、眼精疲労に関連する首・肩・背中の筋バランスをリセットし、血流を促進。ストレッチだけでは届きにくい関節・筋膜へ作用できるのが特徴です。
- 施術内容: 骨盤や背骨のアライメント調整、肩甲骨周りのモビリゼーション、ペアストレッチによる深層筋リリースなど。
- 期待できる効果: 姿勢の改善→頭部・眼への血流改善→眼精疲労軽減。1回で「視界がクリアになった」と感じるケースも。
注意点: 整体師の技術はピンキリであるため、口コミや評判をよく調べ、ご自身が信頼をおける施術者を選択しましょう。
(3) パーソナルトレーナー
パーソナルトレーナーは、筋力・柔軟性・呼吸パターンを総合的に評価し、個別にエクササイズプログラムを設計してくれます。眼精疲労は全身の姿勢バランスと密接に関連するため、トレーニングを通じて“疲れにくい身体の土台”を構築するアプローチが有効です。
- 施術内容: 姿勢評価、呼吸ドリル、視覚トラッキングエクササイズ、肩甲帯・骨盤周りの機能的ストレングス強化など。
- 期待できる効果: 長時間の座位でも崩れにくい姿勢→目や脳の負担軽減→持続的な生産性向上。
メリット: 目先の症状を超えて、根本的に身体を作り替えられる。オンライン指導を併用すれば時間の融通も利きやすい。
注意点: 効果が出るまでに数週間~数カ月の継続が必要。
相談先を選ぶ3つの基準
- 目的: 症状緩和なのか、根本改善なのか。
- 時間軸: すぐに結果を求めるのか、長期的に取り組めるのか。
- コスト: 保険診療か自費か、サブスク型か単発か。
自分の生活リズムや価値観に合った方法を選ぶことが、眼精疲労対策を習慣化させるカギです。
まとめ:今日から始める眼精疲労対策

- 眼精疲労は「目の問題」だけでなく全身の生産性を左右する重要課題
- 視覚過負荷→脳疲労→集中力低下→ミス増加という“負の連鎖”を断つには構造的アプローチが必須
- 作業環境の見直し、セルフストレッチ、専門家への相談を“三本柱”で組み合わせると効果が高い
詳細チェックリスト
- 眼精疲労のメカニズムと症状を理解し、セルフチェックで現状を可視化
- 生産性への影響を定量・定性両面から認識し、対策の優先順位を決める
- デスク環境・姿勢・休憩リズム・栄養の四位一体で“疲れを生む仕掛け”を排除
- アイソメトリック視点移動や肩甲骨リリースなど、即効性の高いストレッチを“トリガー化”して習慣化
- 症状が重い場合は、医療機関で疾患を除外しつつ整体ストレッチやパーソナルトレーナーで根本改善を図る
- KPIと報酬を設計し、チームで取り組むことで継続率と成果を最大化
明日へのアクション
- まずはモニター距離を1.5倍に調整し、20-20-20ルールのタイマーをセット
- メール送信後の30秒ストレッチを“新たな習慣”として登録
- 週末は整体ストレッチ体験にトライし、首肩の血流をリセット
「今日動けば、明日の視界は変わる」。目のコンディションを制する者は、ビジネスの成果をも制します。ぜひ、できることから一歩踏み出してみてください。
参考文献
- 小児のブルーライトカット眼鏡装用に対する慎重意見(声明) ― 日本眼科学会・日本眼科医会ほか6団体(ブルーライトと眼精疲労に関する科学的根拠の整理)
- Digital Devices and Your Eyes ― American Academy of Ophthalmology(瞬目低下・デジタル眼精疲労の実践的対策)
- Digital Eye Strain: Updated Perspectives ― 2024年 総説(20-20-20ルール等のエビデンスと限界を含む最新レビュー)
- Blue-light filtering spectacle lenses for visual performance, symptoms and macular changes: a systematic review ― 2023年 システマティックレビュー(ブルーライトカット眼鏡の有効性は限定的)
- A toolkit on how to implement MyopiaEd ― WHO(近業・スクリーン時間と目の健康に関する行動介入の枠組み)