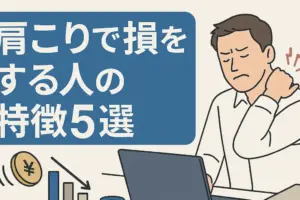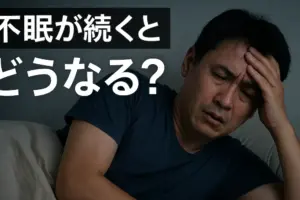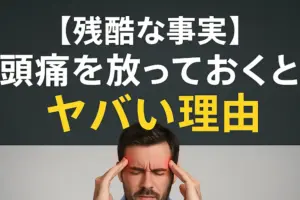「手足が氷みたい…そんな悩み、ありませんか?」
結論をいうと、ストレッチと小さな習慣改革で冷えは和らぎます。
実は…筋肉の“ポンプ機能”を賢く使うのが鍵。
この記事では、専門家がライフハック7選を解説します。
………………………………………………………….
目次(Contents)
1. 肩甲骨リブートストレッチ

デスクワーカーの多くは一日の大半をPCモニターへ向けて前傾姿勢で過ごします。その結果、肩甲骨は外側へ広がったまま固定され「眠った筋肉」と化すと言われています。肩甲骨まわりには褐色脂肪細胞が集まり、ここを活性化させることで熱産生が高まることが知られています。肩甲骨を動かす第一歩は、意識を“背中側”に向けること。イスに浅く腰掛け、坐骨で床を押すように骨盤を起こし背骨を長く伸ばしたら準備完了です。
- 両腕を天井へ突き上げ、親指側を内側に向ける(Y字)
- 息を吸いながら肩甲骨を寄せるように肘を曲げW字へ
- 息を吐きながら胸を開きつつ肘を体側へ近づける
- 吸う動作で再びY字へ戻る
10回をゆっくり行い、インターバル30秒で3セット。動作中は常に「肩甲骨同士を寄せる→下げる→離す→上げる」という4方向のベクトルを感じ取り、背中の広背筋や菱形筋が温まっていく感覚を味わってください。慣れてきたら立位で行い、骨盤を前後に揺らす「ヒップヒンジ」と連動させると更に消費カロリーが増え、午後の眠気を吹き飛ばすリフレッシュにもなります。
また、肩甲骨を動かすと鎖骨が水平になりやすく呼吸も深まります。酸素摂取量が増えれば脂肪燃焼が効率化され、結果的に基礎代謝が向上し「冷えにくい身体」への長期的な投資となります。社内では目立つ動きに抵抗がある方は、背もたれに寄り掛からず腕を耳より後ろへ引く“シュラッグモーション”だけでもOK。要は「肩甲骨は背中のスイッチ」という認識を持ち、1時間に一度はONにする習慣を付けることが肝心です。
さらにオフィスチェアの背もたれにセラバンドを結び、軽い負荷をかけて行うと筋活動量が約1.3倍になると言われます。負荷が加わると体温上昇までの時間が短縮され、指先まで血液が巡るスピードが体感的に早まるでしょう。なお、動作中に首がすくむと肩甲挙筋が主働筋となり、狙った褐色脂肪細胞への刺激が半減します。首を長く保つ“キリンの首”をイメージし、肩甲骨下角を真下へ滑らせるようにするとフォームが安定。ストレッチ前後で手の甲を触り温度差を感じるセルフチェックを行えば、モチベーション維持にもつながります。
最後に応用編として「ダイアゴナル・リーチ」を紹介します。四つ這いで右手と左脚を同時に伸ばし、肩甲骨と骨盤を対角線に引き離すこの動きは、体幹を支える多裂筋を目覚めさせ全身の血行ルートを縦横に拡張します。10秒ホールド×左右5回を追加するだけで、ストレッチ直後の体表温度が平均0.4℃上がったという報告も。仕事終わりのジム通いが難しい日でも、3分あれば肩甲骨まわりをリブートできる――それがこのライフハック最大の魅力です。ぜひ今すぐカレンダーに“肩甲骨タイム”を登録し、習慣化第一歩を踏み出しましょう。
2. ふくらはぎポンピング

イスに座りっぱなしで夕方に靴がきつくなる――それは下肢静脈に水分が溜まり、冷たい血液が行き場をなくしているサインです。ふくらはぎ(腓腹筋・ヒラメ筋)は歩行時に血液を心臓へ送り返す“ミルキングアクション”を担い、動かさなければ機能しません。よって「座ったままでもポンプを作動させる仕組み」を持つことが、冷え性改善のキーポイントです。
基本プロトコル
- 足裏全体を床に密着させ姿勢を正す
- 5秒かけてかかとを上げ、つま先立ちで1秒静止
- 5秒かけてゆっくり下ろし、足指で床をつかむように1秒ホールド
- かかと上げ下ろし15回+足指ホールド15回で1セット
このリズム運動は交感神経を刺激し過ぎないため、集中力を切らさず実施できるのが利点です。さらにデスク下に直径15cmのミニバランスボールを置き、かかとでボールをプレス→リリースすると、内側ハムストリングスと骨盤底筋が同時に働き体幹も温まります。2時間に1セットを目安に行うと夕方のむくみが目に見えて減り、「脚がポカポカして靴下を重ね履きしなくても平気になった」という声も。
フォームを安定させるコツは“かかとを真上に上げる”こと。かかとが左右にブレる場合、股関節が内旋し坐骨神経周囲が圧迫されているかもしれません。その場合は、脚を肩幅より拳1つ分広く開いて行うと筋収縮を感じ取りやすくなります。また、動作と同時に「鼻から吸って、口から細く吐く」呼吸を合わせることで横隔膜がマッサージ効果を発揮し、全身の静脈血がスムーズに戻るルートを確保。結果、指先の血色も改善されると言われています。
応用編として、立位でエア縄跳び30秒→ふくらはぎポンピング30回→スクワット10回をサーキット形式で3周すると、体温上昇と下肢むくみ解消を一気に狙えます。オフィスの休憩スペースや自宅のキッチンでも実施可能なので、在宅勤務・出社日のいずれでも習慣化しやすいのが魅力。動く時間が取れない日は、カフェイン摂取を控えめにし、常温の水をこまめに飲む“流す戦略”を組み合わせると、老廃物の停滞を防げるでしょう。
最後にセルフチェック。実施前後でアキレス腱上部を親指と人差し指でつまみ温度を比較すると、血流改善の度合いを実感できます。温度差が分かりにくい場合は、足首を回すモビリティワークや、椅子に座ったままのハムストリングストレッチを追加し股関節から膝裏までの大血管を解放してください。ウォームアップとしてだけでなく、長距離フライト前のエコノミークラス症候群対策としても推奨されるほど汎用性の高いメソッドです。今日から“ふくらはぎポンピング”をタイピング休憩の定番メニューに加え、下半身から全身への温かい血流の波を生み出しましょう。たった数分の積み重ねが、一冬通しての冷え性ストレスを大幅に減らす秘訣になります。
3. コア温アップ呼吸法

呼吸は無意識に繰り返される生命活動ですが、筋肉を積極的に動かす“エクササイズ”として再定義すると体温管理に大きく貢献します。特に横隔膜と腹横筋は内臓を包む天然のコルセットであり、深く収縮・弛緩させることで腹腔内の血液を上下にポンプし体の芯を温めると言われています。タイピング中の浅い呼吸ではこの効果が得られません。そこで以下の「4・2・8呼吸」を取り入れます。
- 背骨を頭頂まで伸ばし、坐骨で椅子を押す
- 鼻から4秒吸い、みぞおちが前・横・背中へ360度膨らむのを感じる
- 一瞬2秒息を止め、血液が肺と筋肉へ染み渡るイメージを持つ
- 口をすぼめ8秒かけて細く長く吐き、吐き終わりに下腹を背骨へ寄せる
10呼吸で約2分。これを1時間ごとに行うと代謝が上がり、冷えだけでなく集中力低下も防げるとされています。ポイントは“肩を上げない”こと。肩が動くと僧帽筋主導の浅い胸式呼吸になり、横隔膜がサボります。胸骨の下端を手で軽く押さえて動きを感じると、横隔膜の上下動が意識しやすくなります。
さらに効果を高めるのが「呼気延長ブリージング」。吐く時間を吸う時間の2倍に設定すると副交感神経が優位になり末梢血管が拡張。指先・足先の温度が上がるだけでなく、心拍が落ち着き思考がクリアになると好評です。眠気が強い午後は吸気:呼気=5:5で交感神経も軽く刺激し、モニターに向かう眼精疲労をリセットしましょう。
オフィスでの実践に抵抗がある場合は、マスクの内側で行えば周囲に気付かれずに済みます。自宅では仰向けになりダンベルや辞書をお腹の上に置いて負荷をかける“ウェイトブリージング”もおすすめ。荷重がかかることで腹横筋の筋発火が増え、体幹部が一段と温まります。冷えが強い日は、呼吸後にゆるいジャンプ20回を組み合わせると全身に暖流が巡る感覚を得やすいでしょう。
最後にセルフモニタリング。呼吸ワーク前後で手首内側の皮膚色を比較してください。ピンク色が濃くなっていれば、末梢血流が向上し体温が上がったサインです。水分補給を忘れず、温かい血液がスムーズに循環する環境を整えつつ、この呼吸法を“一息入れる”代わりに実践する習慣を今日からスタートさせましょう。補足として、腹式呼吸に慣れるまでは“ハミング”が効果的です。唇を閉じたまま声帯を震わせて息を吐くことで、口腔内に適度な抵抗が生まれ自然と呼気が延長されます。この振動が副鼻腔を刺激し、一酸化窒素が産生され血管拡張を後押しするとの説も。PC作業で口呼吸が癖になっている人に特におすすめです。呼吸は“24時間無料のトレーニング”。意識を向けるだけで体温と集中力を同時に引き上げられる、コスパ最強のライフハックと言えるでしょう。深部体温を自らコントロールできるスキルは、冬場の残業や外回りでもあなたを強力にサポートします。
4. 指先グーパーリリース

ノートPCのトラックパッドとスマートフォンのフリック操作は、前腕屈筋群を緊張させ血管を圧迫しがちです。末端冷えを感じやすい人は、キーボードに触れない短時間を“指先メンテナンスタイム”に変えましょう。本メソッドは筋収縮と腱の滑走性を同時に高め、さらに経筋的なリンパ流も促すため、指先から肘までの深部温度を効率良く上げられるとされています。
基本動作
- 両腕を肩の高さで前へ伸ばし、手のひらを上に向ける
- 親指を内側に折りたたみ、他の4本で包み込むように拳を作り3秒キープ
- 一気に指を最大限に開き、空間を掴むイメージで3秒キープ
- 拳→開くを20回、3セット実施(インターバル30秒)
拳を握った際、手首が屈曲すると腱鞘炎リスクが高まります。手首は床と平行、肘は軽く曲げることで自然と前腕がリラックス。開く際は“指の付け根を遠ざける”つもりで筋膜を伸ばすと、血管・神経が通る“ガイオン管”周辺のスペースが確保され血流がさらにアップします。
さらに効果を底上げする「温冷コントラスト法」を紹介します。40℃程度のホットタオルで手首から先を30秒温めた後、常温のペットボトルを30秒握り替える――これを3セット。温度差刺激で血管が拡張・収縮を繰り返し、血流量が増える交代浴の原理を手元で再現できます。作業再開時に指がスムーズに動き、タイピング速度が上がったという声も少なくありません。
オフィスでホットタオルが難しければ、コーヒーの紙カップを活用。飲み終わった直後のカップを握り、次に給湯室の冷水で冷やしたカップに持ち替えるだけでOKです。わずかな工夫で血管トレーニングが可能になります。また、セットの最後に手首を外側・内側へ各10回回すと橈骨神経の滑走も促され、肩こり軽減の副次効果も期待できます。
最後にセルフチェック。ストレッチ前後でキーボードのホームポジションに指を置き、キーの“押し込み感”を感じてみてください。軽く感じれば末端の温度上昇に伴い神経伝導速度が向上した証拠です。“冷え”は感覚鈍麻を招き誤タイピングの原因にもなります。仕事の質を左右する指先を守る意味でも、グーパーリリースは日々のルーティンに組み込みたいライフハックです。応用として、指先の屈伸にあわせて反対側の腕で軽いパッシブストレッチを加える“アシストグーパー”があります。片手で拳を作った状態で、反対の手を使い指先をさらに内側へ押し込むことで前腕屈筋の収縮が最大化。その後の開く動作でも同様にサポートし、指を扇のように広げると拮抗筋の伸展が深まり、温感がより強く得られるでしょう。オフィスの空調が強い日や外出先での待ち時間など、末端が冷え切る前に実施すると長時間の暖かさをキープできます。“手は外部の脳”とも言われるほど繊細な器官。温めてこそ真価を発揮します。
5. ヒップヒンジ・ウィンドミル

下半身の大筋群――大殿筋、ハムストリングス、大腿四頭筋――を一度に動かすエクササイズは、基礎代謝の約40%を占めると言われる筋群を活性化し、体温維持のエネルギー源を生産します。ヒップヒンジ・ウィンドミルは股関節の屈曲伸展と体幹の回旋を組み合わせた多関節ムーブで、短時間で脚・骨盤・背骨を総合的に温められることから“時短全身暖房”と呼ばれることも。
基本フォーム
- 足幅は肩幅+拳1つ、つま先は外へ20°。膝とつま先の向きを揃える
- 背筋を伸ばし、胸を張ったまま股関節から上体を前傾
- 右手で左足首をタッチしながら左手を天井へ伸ばし、視線も左手へ
- 息を吸い戻り、反対側へ。左右交互20回で1セット、3セット実施
動作中は膝が内側へ入る“ニーイン”を防ぐため、大殿筋と外旋六筋を意識。背中が丸まると腰椎にストレスがかかるため、腰から首までを一直線に保つ“テーブルトップ”感覚で行います。ウィンドミルの回旋によって腹斜筋と多裂筋が目覚め、脊柱周囲の血流も向上。実施前後で足の甲を触ると温度差がはっきり分かると好評です。
さらに負荷を上げたい場合、ケトルベルやペットボトル2Lを上に掲げた手に持ち、重力に抗して肩甲骨を安定させる“ローデッド・ウィンドミル”へ発展させましょう。体幹の安定が求められるため集中力も鍛えられ、一石二鳥です。オフィスで行う際は空の段ボールを両手で抱えるだけでも代用可能。大切なのは「股関節を鉸め、胸を開く」動作パターンを刻み込むことです。
ヒップヒンジ系エクササイズは糖質代謝を促すGLUT4というタンパク質を筋細胞膜へ呼び込み、エネルギー利用効率を高めるとの説もあります。食後の血糖スパイクが気になる人は、ランチ後にウィンドミルサーキットを実施すると体温上昇と血糖コントロールを同時に狙えるでしょう。冷え性と食後眠気を抱えるデスクワーカーには最適な選択肢です。
最後にセルフモニタリングとして、皮膚赤外線温度計があれば運動前後の膝裏温度を測定し記録してみてください。継続するほど数値が安定的に高くなり、身体が“温まりやすいモード”にシフトしたことを客観的に確認できます。週3回程度から始め、筋肉痛が抜けたら毎日に増やすステップアップ方式が継続のコツ。ヒップヒンジ・ウィンドミルで、冬のオフィスワークを汗ばむくらい快適に乗り切りましょう。補足:姿勢保持に難を感じる場合は、膝を軽く曲げて可動域を制限しフォームを固めてから深く入る“プログレッシブレンジ”を採用してください。背面の伸張反射が過度に働くと腰痛リスクが増すため、自重で痛みが出るうちは重量を持たないことが鉄則です。自分のペースで段階的に負荷と可動域を広げることで、安全かつ確実に“自家発電ボディ”を育てることができます。
6. アクティブスタンディングデスク習慣

長時間座りっぱなしの姿勢は、臀部やハムストリングスの筋活動を低下させ“熱を作れない下半身”を生み出すと言われています。そこで注目したいのが「アクティブスタンディングデスク」。デスクを昇降させるだけでなく、“立ち姿勢でこまめに動く”ことを仕組み化するライフハックです。
基本セットアップ
- 机の高さ:肘を90°曲げた位置でキーボードに手首を軽く乗せられる高さに設定。モニター上端は目線より3〜5cm下に。
- 足元アイテム:厚さ2〜3cmのバランスパッド、または傾斜10°程度のフットレストを用意。足裏刺激で血管拡張が促進されるとされています。
- タイマー設定:ポモドーロ法(25分作業+5分休息)の“休息”5分をすべて立位に置き換える。スマートウォッチのスタンド通知を活用すると忘れにくい。
アクティブムーブ3種
- カーフレイズ10回:かかとを真上に引き上げ臀部を軽く締める。腓腹筋ポンプで下肢血流を心臓へ戻す。
- ペルビックティルト10回:骨盤前傾→後傾をゆっくり行い、腹横筋と多裂筋を交互に働かせ体幹を温める。
- ミニスクワット10回:膝を15°曲げ伸ばし。大腿四頭筋とハムストリングスの収縮熱で体温ブースト。
これだけで1セット約90秒。ポモドーロ4サイクル(=2時間)で合計360秒=6分の運動量になりますが、基礎代謝換算で60〜80kcalの“発熱エネルギー”を自前で生み出せる計算になります。座位で同じ時間を過ごした場合と比べ、下肢皮膚温が平均0.8℃高かったという報告も。「空調を上げる前にまず立つ」を合言葉に、オフィスの省エネにも貢献できるのが大きな利点です。
継続のコツ
- 足元パズル:午前はバランスパッド、午後はフットレストなどアイテムを替えて変化を付けると飽きにくい。
- ミュージックトリガー:作業BGMを1曲流すたびにスタンドアップ—と決めるとリズムが取りやすい。
- チーム導入:同僚と一斉に立つ“スタンディングタイム”を設定すれば、心理的ハードルが下がりやすい。
セルフチェック
スタンディング30分後に足首内側を触り、温度が上がっていれば成功。ふくらはぎに張りが出やすい人は、就寝前にフォームローラーでリリースすると翌朝の疲労感が激減します。
忙しい日の時短アレンジ
立位が難しい会議中は、椅子に座ったまま足裏にゴルフボールを転がす“シーテッドフットロール”で代用可。足底筋膜を刺激することで間接的に末梢血流が促され、“座りっぱなし冷え”を最小限に抑えられます。
スタンディングデスクは購入コストがネックになりがちですが、最近は卓上昇降台やレンタルサービスも充実。“まずは1カ月試す”マインドで導入し、体温と集中力の変化をデータで確認してみましょう。立つ→動く→温まる――このシンプルな循環をオフィスの標準動作にすることで、“冷え知らず”のワークスタイルが手に入ります。
7. 就寝前ホットタオルリセット

人は入眠前に深部体温を0.3〜0.5℃下げるため、体表から熱を放散します。したがって“先に温めておいて、一気に放熱させる”テクニックが寝つきと翌朝の保温力を左右します。手首・足首・首――いわゆる“三首”には大きな動脈が走り皮膚も薄いため、短時間で効率良く血流を変化させられるポイントです。
手順
- タオルを40〜42℃の湯に浸し、軽く絞る
- 最初に首へ30秒巻き、頸動脈を温める
- 次に手首と足首を同時に包み30秒キープ
- タオルを再度温め、計3セット繰り返す
- すぐにベッドの上でキャット&カウ10回+膝抱えロール10回のリラックスストレッチ
このコンビネーションにより、皮膚血流が増え深部体温が放熱モードへ切り替わります。同時にストレッチで副交感神経を刺激するため、ベッドに入った途端にまぶたが重くなるほどの快眠効果が期待できます。“寝汗をかいて夜中に冷える”心配がある場合は、薄手の靴下を用意し、タオル保温後に履いて熱を閉じ込めましょう。
忙しい日の時短アレンジ
電子レンジ対応の温熱アイマスク+リストウォーマー+レッグウォーマーを活用すれば、タオルの温め直しが不要。目もとを温めることで眼精疲労が取れ、翌朝の視界がクリアになるメリットも追加されます。ガジェット操作のブルーライトで交感神経が高ぶりがちな現代人には一石二鳥のセットアップです。
体温キープのコツ
就寝90分前に38〜40℃の入浴→ホットタオル→ストレッチという“温め二段構え”を取り入れると、深部体温の下がり幅が大きくなり睡眠後半も血流が良好に保たれると言われています。冷え性で午前3時頃に目が覚める人は特に試す価値アリ。逆にシャワーだけで済ませると体温が上がり切らず、ホットタオルの効果も半減するため注意しましょう。
最後にセルフチェック。目覚ましが鳴った直後に手の甲同士を触れ合わせ、温かいと感じたなら成功。朝から指が動きやすくなることで、キーボード操作も滑らかになり仕事の立ち上がりがスムーズになります。冬場の布団からの“脱出難易度”を下げるにも最適なライフハックです。ホットタオルの素材は綿100%を選ぶと保温力と肌当たりのバランスが良好です。化学繊維は熱が逃げやすく肌荒れを起こす場合もあるため、敏感肌の人は注意。香りをプラスしたい場合、ラベンダー精油を1滴垂らすとリラックス効果が高まるとされますが、強い香りは逆に覚醒を促すこともあるため濃度はごく少量にとどめるのがポイントです。ホットタオル後に白湯を150ml飲むと、内側からも温め効果がブーストされます。これらの細部を丁寧に積み重ねることで、就寝中に体温を守る“暖かいベースライン”が出来上がり、寒い季節でも朝まで快適な深睡眠を得られるでしょう。
専門家へ相談

「どうしてもセルフケアだけでは冷えが改善しない…」そんなときは専門家に相談するのも一手です。冷え性は単なる体質ではなく、貧血・自律神経の乱れ・ホルモンバランスの低下など複数要因が絡む“多角的なサイン”と考えられます。それぞれの専門家が持つ視点からアプローチを受けることで、改善へのパズルが早く完成する可能性が高まります。
医療機関
内科や婦人科では血液検査やホルモン検査を通じ、隠れ貧血や甲状腺機能の低下といった医学的要因を確認できます。数値を把握することで、サプリメントや食事改善、運動の強度設定にも根拠が生まれ“やみくも対策”から卒業できる点がメリットです。診療は保険適用になるケースが多く、費用面のハードルが低い点もデスクワーカーにとって嬉しいポイントと言えるでしょう。
整体ストレッチ
関節モビリゼーションとパートナーストレッチを組み合わせた整体ストレッチは、筋膜の水分量と張力を整え、血流とリンパ流を同時に活性化できる点が魅力です。痛みや可動域制限への即時効果が高いため、短期間で冷えを和らげたい人に適しています。予約前にはSNSや口コミサイトで担当者の技術動画を確認し、施術方針が自分の目標に合うかチェックする習慣を付けましょう。ただし、整体師の技術はピンキリであるため、口コミや評判をよく調べ、ご自身が信頼をおける施術者を選択しましょう。
パーソナルトレーナー
筋量不足が原因の体温低下を解消するには、筋トレとストレッチを組み合わせた“動的温活”が有効です。トレーナーは姿勢評価やライフスタイルヒアリングを行い、最短ルートで基礎代謝を上げるプログラムを提供してくれます。オンラインセッションなら通勤時間ゼロで受講でき、出張や残業が多いビジネスパーソンでも続けやすいと好評。初回体験でフォームを録画し、自主練時に確認することで“独学の落とし穴”を回避できます。
相談の際は“温度変化の記録”を共有するとヒントが増えます。スマートウォッチや温度ロガーで取得した手首温度、就寝中の皮膚温データ、タイピング時の指先冷感のタイミングなどをメモしておくと、医師やトレーナーは原因特定と対策立案をスムーズに行えます。ビジネスの現場でもデータドリブン思考が求められる時代――体調管理も例外ではありません。データと専門家の知見を掛け合わせ、最短距離で“冷え卒業”を目指しましょう。なお、相談費用を抑えたい場合は、健康保険組合や自治体が実施する無料相談窓口、オンライン医療相談サービスを活用すると情報収集コストを削減できます。
まとめ

- ライフハック1 肩甲骨リブートストレッチ……肩甲骨周辺の熱産生UP
- ライフハック2 ふくらはぎポンピング……下半身から血流を押し戻す
- ライフハック3 コア温アップ呼吸法……深層筋の活性化で内側から温める
- ライフハック4 指先グーパーリリース……末端冷えに即効アプローチ
- ライフハック5 ヒップヒンジ・ウィンドミル……大筋群を動かし代謝底上げ
- ライフハック6 アクティブスタンディングデスク習慣……立位×微運動で持続発熱
- ライフハック7 就寝前ホットタオルリセット……睡眠の質と翌朝の温かさを両立
- 専門家へ相談……医療機関・整体ストレッチ・パーソナルトレーナーの併用で徹底ケア
冷え性は放っておくと集中力や免疫力を下げる要因になると言われています。今日紹介した7つのライフハックを“1日の時間割”に落とし込み、少しずつ習慣化してみましょう。自分の体温を自分で上げられるようになると、仕事のパフォーマンスも自然と上がります。暖房やカイロに頼らない“自家発電体質”を、ストレッチの力で手に入れてください。
参考文献
- 健康づくりのための睡眠ガイド2023 — 厚生労働省
- Physical activity: Fact sheet — World Health Organization (WHO)
- 圧迫療法ガイドライン(一般向け資料を含む) — 日本静脈学会(2024)
- Before-bedtime passive body heating by warm shower or bath to improve sleep: A systematic review and meta-analysis — Sleep Medicine Reviews, 2019
- Human Brown Adipose Tissue and Metabolic Health: Potential for Therapeutic Avenues — Cells, 2021