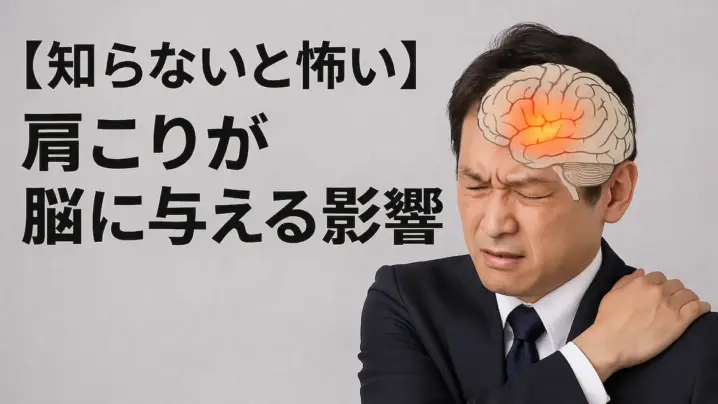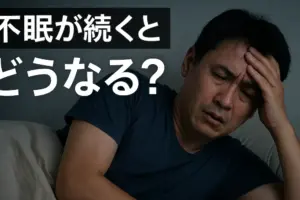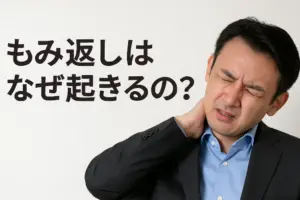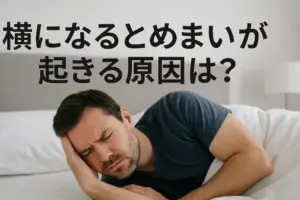「最近、集中力が続かない…」そんな悩みはありませんか?
結論をいうと、その原因は“肩こり”かもしれません。
実は…肩の筋緊張は脳血流を阻害し、思考力まで低下させるおそれがあります。
この記事では、ストレッチの専門家が原因と対策を徹底解説します。
………………………………………………………….
目次(Contents)
そもそも肩こりとは何か?

肩こりとは、首から肩甲骨周辺にかけての筋肉が持続的に緊張し、硬くこわばった状態を指します。デスクワーカーに多い原因としては、長時間の前傾姿勢、同じ画面を見続けることによる眼精疲労、運動不足、そして心理的ストレスが挙げられます。筋肉が緊張すると血管が圧迫され、酸素や栄養が行き渡りにくくなるため、疲労物質が蓄積して重だるさを感じるようになります。
さらに、PCやスマートフォンを操作する際、頭部が本来の位置より前に突き出る「フォワードヘッド姿勢」が習慣化することで、首の後ろの筋肉が常に頭の重さを支えることになり、負荷が増大します。一般的に成人の頭部は体重の約10%、ボウリング球1個分ほどの重さといわれていますが、頭が前方に3cm傾くだけで首への負担は約2倍に跳ね上がると言われています。
また、冷房による冷えや睡眠中の枕の高さが合わないことも筋緊張を助長するため注意が必要です。こうした多因子的な要素が絡み合うことで慢性的な肩こりが生まれ、やがて痛みだけでなく集中力の低下や気分の落ち込みなど、全身状態に影響を及ぼすケースが少なくありません。つまり肩こりは単なる局所的な不快感ではなく、生活の質(QOL)全体を左右するサインと捉えることが重要です。
デスクワーカーが1日8時間座ってキーボードを打ち続ける環境では、肩と首の動きが極端に制限されます。筋肉は動かさない時間が長いほど血流が滞るため、酸欠状態となり、神経は痛みや不快感を増幅させて危険信号を脳へ送ります。その結果、仕事が長引くほど肩こりが強まり、ストレスホルモンであるコルチゾールが分泌されやすくなるとされています。コルチゾールは短期的には集中力を高める働きがありますが、慢性的に高まると免疫力を下げたり、睡眠の質を落としたりする可能性が高まります。
このように肩こりは身体的ストレスと精神的ストレスの双方を悪循環させる要因となるのです。ビジネスパーソンにとって「肩こり=単なる疲れ」と軽視することは、長期的な生産性の低下を招くリスクといえるでしょう。実際に「肩が重い」「首が回らない」という自覚症状が出る前から筋硬直は進行しているといわれており、早期のケアが欠かせません。次の章では、この肩こりがいかに脳へ影響を及ぼすのか、そのメカニズムを詳しく見ていきましょう。
さらに、テレワークによってオフィス環境から解放された一方で、自宅のダイニングチェアやソファで長時間作業を行う人が増えています。これらは人間工学に基づいたデスクチェアと比べてサポート機能が不足しているため、背骨の自然なS字カーブが崩れやすく、肩こりを助長する大きな要因になります。日常的に肩甲骨周囲の筋肉や胸郭の可動域を広げるストレッチを行うことで、血流を改善し、肩こり予防につながることは多くの現場で実証されています。
以上を踏まえると、肩こりの本質は「筋肉が動かない時間の長さ」と「不良姿勢による荷重の偏り」にあり、それらを解消する第一歩は“こまめに動かす”ことと言えます。
肩こりが脳へ及ぼすメカニズム

肩周辺の筋肉が長時間硬直すると、僧帽筋や後頭下筋群を走る血管・リンパ管が圧迫され、脳を養う椎骨動脈系の血流が低下しやすくなると語られています。血流が低下すると、脳へ供給される酸素とブドウ糖の量が不足し、エネルギー代謝が落ち、神経伝達物質の合成に影響を与える恐れがあります。これにより、注意力やワーキングメモリが低下し、判断ミスや作業効率の悪化が生じやすいとされています。
さらに筋緊張そのものが痛みの受容体を刺激し、脳の痛覚領域である体性感覚野や前頭前野を過剰に活性化させることで、疲労感やイライラ感を増幅させると考えられています。特にデスクワーカーはPC画面を凝視することで瞬きの回数が減り、眼球周囲の筋肉が緊張する「VDT症候群」も併発しやすく、視覚からの刺激がさらにストレスを助長します。ストレスが蓄積すると、自律神経系のうち交感神経が優位になり、末梢血管が収縮して血圧が上昇、肩こりはより悪化するという負のスパイラルに陥りがちです。この状態が慢性化すると、睡眠中も筋緊張が解けず、深い睡眠に不可欠なノンレム睡眠が減少し、翌朝起床時から疲労感を覚えることになります。
脳科学の視点で見ると、慢性的な筋緊張は扁桃体の過活動につながり、危険信号を誇張して認識させるため、不安感が高まりやすい傾向も指摘されています。長期的には、このような慢性的ストレスは海馬の可塑性にも影響し、記憶形成効率の低下、さらにはうつ傾向のリスク増大にも結びつく可能性が示唆されています。つまり、「肩がこるだけ」と放置すれば、脳のパフォーマンス低下、メンタルヘルス不調など、多岐にわたる悪影響がドミノ倒し的に広がるおそれがあるというわけです。
ここまで読むと不安になるかもしれませんが、適切なストレッチと生活習慣の改善を行えば、血流と自律神経のバランスを整え、脳機能を回復させることが十分に期待できます。次章では、肩こりを抱えるデスクワーカーが遭遇しやすい具体的なリスクシーンと、脳疲労を最小限に抑えるためのポイントを解説します。なお、脳は体重の約2%の重さでありながら、安静時でも全身の20%を超える血流を必要とすると言われています。
そのため、肩こりが首周囲の血流を阻害し始めると、脳はただちにエネルギー不足に陥り、代償として周辺組織からの血液を取り込もうと心拍数を上げます。この反応が繰り返されると、仕事中にも関わらず心拍数が高めの状態が続き、軽い息切れや動悸を感じるケースも少なくありません。加えて交感神経優位が続くと胃腸の働きが抑制されるため、食欲不振や慢性的な便秘・下痢が起こることもあり、結果として栄養吸収が不安定になり脳へのエネルギー供給はさらに低下します。
この負の連鎖を断ち切るためには、首・肩周りの筋緊張を解放し、血流を促進するストレッチやモビリティエクササイズを定期的に取り入れること、そして短時間でも質の高い休憩を挟む習慣を構築することが有効です。
デスクワーカー特有の肩こり・脳疲労リスク

都内のオフィスビルや在宅勤務でモニターに向かうデスクワーカーは、一日平均で約9時間以上座っているといわれています。長時間座位は骨盤を後傾させ、胸椎の後弯を強め、結果として頭が前に滑り出す姿勢を固定化します。この姿勢では、僧帽筋上部線維と肩甲挙筋が頭の重量を支え続けるため、筋緊張が高まるのは避けられません。
加えて、マルチディスプレイやノートPC+外部キーボードなど複数の入力機器を使う環境では、視線移動・腕の位置が頻繁に変わり、僧帽筋中部や菱形筋にもアンバランスな負荷が生じます。こうした身体的ストレスに加え、タスク管理やコミュニケーションツールの通知による精神的プレッシャーが重なると、脳は常にマルチタスク状態となり、交感神経優位が常態化します。その結果、肩こり悪化→脳血流低下→集中力低下→タスク遅延→精神的ストレス増大→さらに肩こり悪化という「負のループ」が完成してしまうのです。
特にリモートワークでは、オン・オフの切り替えが曖昧になるうえ、昼休憩も画面を見ながら短時間で済ませるなど、身体を動かす機会が大幅に減少しがちです。パフォーマンスの高いデスクワーカーほど「座ったまま粘ることが美徳」と考えがちですが、科学的には60〜90分ごとに2〜3分立ち上がるだけでも、肩周囲の血流量が有意に改善すると言われています。
また、照明のブルーライトやエアコンの風が直接首に当たる環境も、筋血流を阻害し脳疲労リスクを引き上げるファクターです。ここで重要なのは、「環境を整えること」と「短時間でも身体を動かすこと」をセットで習慣化すること。高さ調整が可能なスタンディングデスクに切り替える、モニターを目線の高さに合わせる、タスク管理アプリに休憩リマインダーを設定する、といった仕組み化が行動を後押しします。
さらに、昼休憩には軽いウォーキングや上半身のストレッチを3〜5分取り入れることで、膝下の筋ポンプ作用が働き、首・肩周囲だけでなく脳への静脈還流も促進されます。このような小さな介入が積み重なることで、午後の集中力持続時間が長くなり、結果として仕事の質と量の両面でパフォーマンスが向上するケースが多いとされています。デスクワーカーだからこそ、あえて「動く」時間をスケジュールに組み込み、肩こりと脳疲労を同時にケアする視点が不可欠です。
次のパートでは、肩こりが脳機能に具体的にどのような影響をもたらすのか、サインとパフォーマンス低下の実例を紹介します。特に、午後3時前後のいわゆる「魔の時間帯」は、血糖値の変動と昼食後の副交感神経優位への揺り戻しで眠気を感じやすいタイミングです。この時間帯に肩こり由来の脳血流低下が重なると、想像以上に意思決定力が鈍り、メールの誤送信や仕様ミスなどヒューマンエラーのリスクが跳ね上がるといわれています。
したがって、15時前に立ち上がって肩甲骨を大きく回す、軽いスクワットを10回行う、その後に常温の水をコップ1杯飲む、といったシンプルなルーティンを入れるだけでも、生産性と健康の両立に寄与します。
脳機能低下のサインとパフォーマンスへの影響

肩こりが慢性化すると、脳は酸素と栄養不足をカバーするために省エネモードへ移行し、以下のようなサインが現れやすくなります。
- 些細なミスの増加
- 同僚との会話内容を思い出せない
- 何度読んでも文章が頭に入らない
- アイデアが湧かない・決断力が鈍る
- 仕事終わりに強い倦怠感が残る
これらは一見、単なる疲れや加齢のサインと誤解されがちですが、肩こり由来の脳血流低下が背景にあるケースも少なくありません。たとえば、会議中に発言内容がまとまらない、資料作成に倍以上の時間がかかる、といった生産性の低下は、脳の前頭前野が機能低下を起こしている可能性があります。前頭前野はタスク切り替えや意思決定、創造的思考を司る領域で、血流が不足すると「フロー状態」に入りにくくなり、仕事の質が大きく損なわれます。
さらに、眼精疲労からくる視覚情報処理の遅延は、後頭葉の負担を増やし、ミスの連鎖を誘発します。こうした脳機能低下は短期的には仕事の遅延、長期的には評価やキャリア形成へ悪影響をもたらし、経済的損失へと直結するリスクさえあります。
また、脳のエネルギー不足が続くとドーパミン分泌が減少し、モチベーション低下や快楽の喪失(アネドニア)といったメンタルヘルス不調が進行しやすくなると言われています。この状態が続けば、睡眠障害や食欲不振、さらには適応障害・うつ状態に発展する可能性も否定できません。反対に、肩こりを適切にケアし血流を回復させることで、わずか数日でも「頭の回転が速くなった」「朝の目覚めがスッキリした」といったポジティブな変化を感じる人も多いのが現実です。つまり、肩こり対策は単なるコンディショニングではなく、ビジネスパフォーマンスを底上げする“投資”と捉えるべきでしょう。エネルギッシュに働き続けるには、“脳を守る肩まわりケア”という意識改革が不可欠です。
次章では、今日からオフィスや自宅で実践できるストレッチ&エクササイズを具体的に紹介します。パフォーマンスを数値化すると、脳機能低下はタイピングエラー率の増大や、プレゼン資料校正に要する時間の延長として表出します。会議中の発言では、言葉を選ぶまでの“間”が長くなり、「要は何が言いたいの?」と質問を受けるシーンが増えるとも言われています。集中力が途切れると、脳はタスク間スイッチングに余計なエネルギーを割くため、結果として一つ一つの仕事にかけるリソースが不足し、質の低下を招きます。こ
のように、肩こり放置は自己効率の損失のみならず、組織全体のパフォーマンスにも波及しかねない問題なのです。幸い、脳は可塑性を持ち、“使えば鍛えられる”臓器です。肩こりを改善し、十分な血流と酸素を供給することで、神経回路の働きは驚くほど早く回復するケースも多く報告されています。よって、自身の「脳機能低下サイン」に敏感になり、肩こりを疑ったら即アクションを取ることが、キャリア形成や自己成長の土台となります。
自宅・オフィスでできる肩こり予防ストレッチ&エクササイズ

ここでは、時間と場所を選ばず実践できる4つのメソッドを紹介します。各エクササイズは30〜60秒で完了するので、仕事の合間に取り入れてください。
1. ショルダーシュラッグ+深呼吸
椅子に浅く座り、両腕をリラックスして下ろします。息を吸いながら肩を耳に近づけるように持ち上げ、3秒キープ。吐きながらストンと肩を落とし、肩甲骨を下制します。呼吸と連動させることで副交感神経が刺激され、首まわりの血流を促進します。
2. 胸開きダイナミックストレッチ
立位で両腕を肩の高さに前ならえし、手のひらを合わせます。息を吸いながら腕を左右に大きく開き、肩甲骨を寄せ、胸郭を広げます。吐きながら元の位置へ戻り10回繰り返します。胸椎伸展を促すことで頭の前方移動をリセットし、脳へ向かう血流をキープできます。
3. チェアツイスト&アイフォーカス
椅子に座ったまま背筋を伸ばし、右手を左太ももの外側に置きます。息を吐きながら上体を左にひねり、視線も後方へ送ります。このとき、焦点を遠→近→遠と3点切り替えて眼球運動を追加することで、VDT症候群の予防にもなります。左右各5回。
4. スタンディングT字アームリフト
足を骨盤幅に開いて立ち、両腕を体側へ下ろします。手のひらを前に向けながら腕を横から上げ、肩の高さでT字に。さらに親指を後方へ回すイメージで肩甲骨を寄せ、背中上部を活性化させます。呼吸を止めないまま8秒キープし、ゆっくり戻す。3回繰り返し。
実践ポイント
- 1時間に1セットを目安にする
- 痛みが出る場合は可動範囲を小さく調整
- 動作後に常温の水を一口飲み、全身循環を助ける
これらのストレッチをルーティン化することで、筋緊張の慢性化を防ぎ、脳の血流を安定させる効果が期待できます。習慣化しやすいコツとしては、タスク管理ツールに“1時間にストレッチ×1セット”と入力しリマインダーを表示させる、カレンダーに立ち上がる時間をブロックする、同僚と一緒に行うなど、行動のハードルを下げる仕組み化が有効です。
また、リモートワークの場合はカメラをオフにしているタイミングで実践する、オンライン会議後のクールダウンとして取り入れるなど柔軟に組み込みましょう。日常的にこれらの動きを行うことで、肩甲骨周りの滑走性が改善し、上腕骨頭のポジションが整うため、首・肩への負担は劇的に軽減されると語られています。それにより脳血流が安定し、午後のタスクでも集中力が途切れにくくなるでしょう。
さらに、就業前や就寝前にフォームローラーやテニスボールを使用して僧帽筋上部・後頭下筋群をマッサージすると、短時間で筋硬直をリリースできます。ただし、押し過ぎや強過ぎは逆に筋緊張を助長する可能性があるため、痛気持ちいい範囲に留め、30秒以内を目安に行いましょう。これらセルフケアで改善がみられない場合は、専門家のサポートを受ける選択肢も視野に入れてください。次章で詳しく説明します。
生活習慣の総合アプローチで肩こりと脳疲労を断つ

肩こり改善の鍵は、ストレッチのみならず、睡眠・栄養・メンタルケア・作業環境といったライフスタイル全体を整えることにあります。
1. 睡眠の質を高める
枕の高さが合わないと頸椎の生理的湾曲が崩れ、就寝中も筋緊張が続きます。仰向けで寝た際に、鼻と喉が水平になる程度の高さが目安。就寝前のブルーライトカットや室温20〜22℃の維持、寝る前に常温水を250ml飲むなど、睡眠中の血流を保つ工夫も効果的です。
2. 栄養バランスを整える
タンパク質とビタミンB群は筋組織修復とエネルギー産生に欠かせません。朝食に卵と全粒パン、昼食に鶏胸肉と雑穀米、夕食にサーモンと緑黄色野菜を組み合わせるだけでも、脳への栄養供給は大幅に改善します。さらに、マグネシウムを多く含むナッツ類や、オメガ3脂肪酸豊富な青魚・亜麻仁油は、神経伝達の効率を高めるとされています。カフェインは集中力アップに有効ですが、午後3時以降は控えめにしないと睡眠の質を下げ、結果的に肩こり回復が遅れる可能性があります。
3. メンタルストレスをコントロールする
マインドフルネス呼吸法や5分間の目を閉じた瞑想は、自律神経のバランスを整えるうえで即効性があります。呼吸に意識を向けることで、副交感神経が優位になり、首・肩の筋緊張が和らぎやすくなります。ストレッチ前後に10回腹式呼吸を入れるだけでも、筋の伸長反応が高まりやすくなると語られています。
4. 作業環境の最適化
モニター上端が目線より3〜5cm下に来るように設定し、キーボードは肘が90°になる高さに調整しましょう。リフトアップ機能付きノートPCスタンド、外付けキーボード、エルゴノミックマウスへの投資は、肩こりと脳疲労を防ぐ“設備投資”と捉えることができます。照度500lx前後の自然光に近いデスクライトを使用することで、眼精疲労を抑え、生産性向上に寄与するとされています。
5. こまめなマイクロブレイク
25分作業+5分休憩の“ポモドーロ・テクニック”を取り入れ、休憩中にストレッチと水分補給を実施することで、肩周りの血液循環と脳の覚醒度が維持できます。特にデスクワーカーはコップ一杯(200ml)の水を1時間ごとに飲む習慣を持つだけで、脱水による頭痛と血液粘度の上昇を防げるといわれています。
6. 運動習慣を確立する
週2〜3回、1回30分の全身運動(ウォーキング、ジョギング、スイミングなど)を行うと、全身の毛細血管ネットワークが発達し、肩こりだけでなく脳血流も改善します。特に、姿勢筋を強化する自重トレーニング(プランク、バックエクステンション)は、肩こり再発防止に効果的です。
また、週末には自然環境を利用した“深呼吸瞑想ウォーク”を取り入れることで、心肺機能を高めながら肩甲骨の可動域を拡大し、脳へ新鮮な酸素を送り込むことができます。公園を30分歩くだけでも、ストレスホルモンの低下と前頭前野の血流増加が期待できるといわれています。季節や天候に合わせてルートを変えると飽きずに続けられ、単純接触効果で「運動=気持ちいい」というポジティブな連想が深まります。
専門家へ相談するタイミングと選び方

セルフストレッチを継続しても痛みやしびれ、頭痛、吐き気などの自律神経症状が改善しない場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
医療機関
整形外科やリハビリテーション科では、画像検査で頸椎や神経に問題がないかを確認し、必要に応じて物理療法や運動療法を処方してくれます。慢性的な肩こりの裏に頸椎ヘルニアや血管系疾患が潜んでいるケースも報告されているため、まずは医師の診察を受けて安全性を確保すると安心です。
整体ストレッチ
整体ストレッチは「整体のアジャスト技術」と「パートナーストレッチの深層筋を伸ばす技術」のいいとこ取りをしたアプローチです。関節アライメントを整えつつ、セラピストの補助でストレッチングを行うため、自力では伸ばしにくい肩甲下筋や小円筋などの深層筋群にまでアプローチできるのが特徴。血流改善と可動域拡大を同時に狙えるため、脳への酸素供給を回復させるうえで非常に有用とされています。ただし、整体師の技術はピンキリであるため、口コミや評判をよく調べ、ご自身が信頼をおける施術者を選択しましょう。
パーソナルトレーナー
運動習慣がない方や正しいフォームでのエクササイズに自信がない方は、パーソナルトレーナーと一緒に筋力トレーニングとストレッチを併用するのが効果的です。特に肩甲骨周囲筋の筋持久力を高めるプログラムや、胸郭モビリティを改善するドリルを定期的に行うことで、肩こり再発リスクを大幅に減らすことができます。また、姿勢分析アプリなどを用いて客観的なデータを共有するため、モチベーション維持につながる点もメリットです。
専門家選びのチェックリスト
- 施術・指導方針が科学的根拠に基づいているか
- カウンセリングで生活習慣までヒアリングしてくれるか
- 料金体系と通いやすさ(距離・時間)が適切か
- 口コミやレビューで一貫した高評価があるか
これらのポイントを満たす専門家を選ぶことで、肩こりだけでなく全身のパフォーマンス向上へとつながるでしょう。医療機関を受診した後、器質的な問題がない場合でも「何をしても治らない」と感じる人は多いものです。その場合、整体ストレッチやパーソナルトレーニングは、運動機能と姿勢の両面からアプローチできるため、セルフケアと医療のギャップを埋める存在として活用すると良いでしょう。
最近では、オンラインでストレッチ指導を行うトレーナーも増えており、忙しいビジネスパーソンでも隙間時間に専門家のサポートを受けやすくなっています。一方で、SNSや動画サイトで見かける自己流のストレッチやマッサージは、誤ったフォームで行うと逆に筋緊張を強めたり関節を痛めたりするリスクがあるため要注意です。初回は必ず対面またはライブ配信など、リアルタイムでフォームチェックを受けられる環境を選び、正しい身体感覚を身につけましょう。
なお、肩こりは一朝一夕には解消しません。週1回の施術や指導を受けつつ、日常のセルフストレッチを継続するハイブリッド型の取り組みが、最も成果を上げていると言われています。もちろん、費用対効果を考えるうえでコストは気になるポイントですが、「脳の働きを取り戻す投資」という視点で計算すると、十分ペイできるケースが多々あるのも事実です。
まとめ

- 肩こりは血流不足を通じて脳機能を低下させ、集中力・判断力・メンタルヘルスに悪影響を与える。
- デスクワーカーは長時間座位とストレスで肩こりリスクが高く、定期的なストレッチと環境整備が不可欠。
- 自宅・オフィスでできるショルダーシュラッグや胸開きストレッチを1時間ごとに実践し、筋緊張をリセットする。
- 改善が乏しい場合は医療機関で安全性を確認し、整体ストレッチやパーソナルトレーナーのサポートを受けると効果的。ただし、整体師の技術はピンキリであるため、口コミや評判をよく調べ、ご自身が信頼をおける施術者を選択しましょう。
睡眠・栄養・メンタルケア・作業環境・マイクロブレイク・定期運動の6要素を整え、肩こりと脳疲労の負の連鎖を断つ。 肩と脳は“血流”で密接につながっています。今日からできる小さな一歩を積み重ね、仕事のパフォーマンスと健康の両方を高めましょう。あなたの肩こり対策が脳と身体を守り、明日の生産性を作る——その意識を今日から行動に変えてみませんか。さあ、デスクを離れて深呼吸し、肩を回すところからスタートです。
参考文献
- 厚生労働省. 情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン[PDF]
- World Health Organization. WHO Guidelines on physical activity and sedentary behaviour (2020)
- 日本整形外科学会. 「肩こり」患者向け解説
- Albulescu P, et al. “Give me a break!”: A systematic review and meta-analysis on the efficacy of micro-breaks for increasing well-being and performance. PLOS ONE. 2022.
- 日本眼科学会. 眼精疲労(目の疲れ)