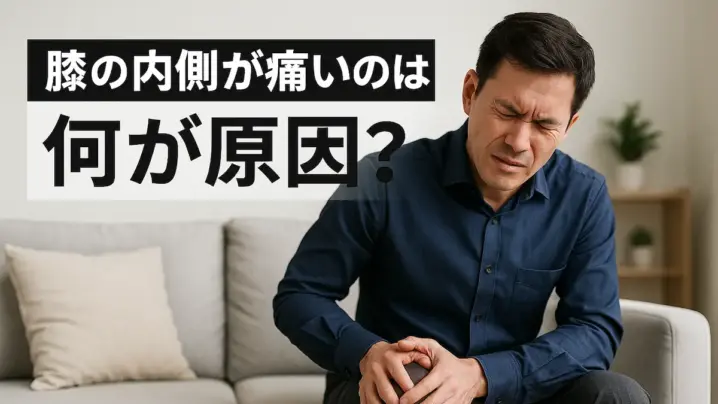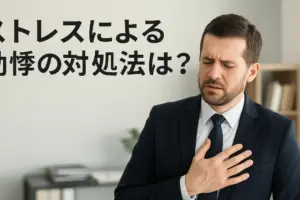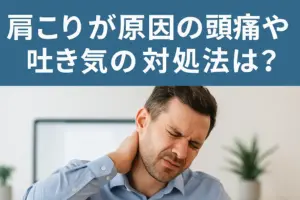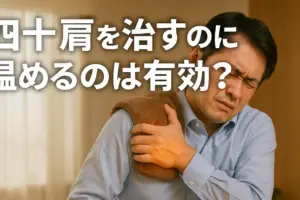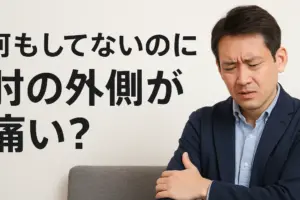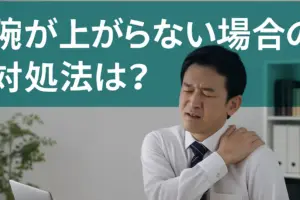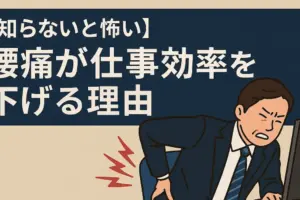デスクワークで長時間同じ姿勢を続けた後、膝を曲げると内側が痛いと感じた経験はありませんか?
結論をいうと、膝の内側に痛みを抱える要因は複数あり、正しい対処法を選ぶことで早期の改善が期待できます。
実は…膝を酷使している方ほどストレッチや生活習慣を見直すだけで大きく症状が緩和するケースが多いのです。
この記事では、ストレッチの専門家が対処法から予防策まで詳しく解説します。
………………………………………………………….
目次(Contents)
1. 対処法
 膝の内側に痛みを感じると、日常生活はもちろん、生産性にも大きな影響が出ます。
膝の内側に痛みを感じると、日常生活はもちろん、生産性にも大きな影響が出ます。
デスクワーク中心の生活を送っていると、意外に歩く機会が少なくなり、脚の筋肉が硬くなったり筋力が低下したりしがちです。
そこでまずは、今すぐできる対処法を中心にご紹介していきます。
冷却や温めによる痛みのコントロール
膝の内側の痛みが強く出ている場合、まずは炎症を抑える目的でアイシング(冷却)を検討しましょう。
冷却により血管が収縮し、痛みのもととなる炎症物質が減少しやすくなります。
やり方はいたってシンプルで、氷のうや保冷材をタオルでくるんで膝の内側に10分ほど当てることを1回の目安にしましょう。
強い痛みが治まってきたら、温めて血行を良くし筋肉の柔軟性を高める方法へ移行すると効果的です。
ただし、冷やす時間が長すぎると逆に筋肉が硬直してしまったり、感覚が鈍くなりすぎたりするので注意してください。
だいたい「10分冷やす→一旦外す→また必要に応じて10分冷やす」という流れが目安です。
痛みの強さによっては医療機関へ相談する必要があるので、冷却や温めだけで改善がみられない場合は放置しないようにしましょう。
簡単にできるストレッチと軽度エクササイズ
膝の内側が痛いときでも、周辺の筋肉を上手にほぐすことで痛みがやわらぐ場合があります。
デスクワーカーや立ち仕事の人は膝まわりの筋肉が硬くなりがちです。
以下に、簡単にできるストレッチと軽度のエクササイズの例を挙げます。
ハムストリングス(もも裏)のストレッチ
太ももの裏側にあるハムストリングスが硬いと、膝の動きが制限され、内側に負担がかかりやすくなります。
イスに座った状態で片足を前に伸ばし、つま先を天井方向へ向けながら腰をやや前に倒します。
痛みのない範囲で20~30秒キープし、反対側も同様に行います。
内転筋(内もも)のストレッチ
内転筋が硬いと膝の内側に負担が集中することがあります。
イスに座って足を肩幅よりやや広く開き、背筋を伸ばして片方の膝を外側に倒すように開きます。
このとき、内ももが伸びる感覚があればOKです。
左右交互に20~30秒ずつ、痛みのない範囲で行いましょう。
スクワット(浅め)
本格的なスクワットは膝に大きな負担をかけることがありますが、膝の状態が軽症なら、浅めのスクワットで太ももの筋力を維持するのも効果的です。
イスの背もたれや机に手を添え、軽く腰を落とす程度でOK。膝がつま先より前に出ないように意識しながら、10回×3セットを目安に行います。
痛みが強くなれば中断し、無理はしないようにしてください。
姿勢や歩き方の見直し
対処法として意外に見落としがちなのが“姿勢”と“歩き方”です。
膝の内側が痛む人の中には、猫背や骨盤の歪みにより膝に負担がかかりやすい姿勢になっているケースがあります。
デスクワーク中は肩が前に出やすく、背中が丸まりやすいので、椅子に座るときは以下のポイントを意識しましょう。
• 足裏は床につけ、膝と股関節は90度程度に保つ
• パソコンの画面は目線より少し下にし、首を過度に前に傾けない
• 椅子の背もたれを活用し、腰が反りすぎないようにサポートする
歩くときは、かかとから着地して足裏全体へ体重移動し、最後につま先で地面を押し出すように意識すると膝への負担が軽減されます。
長時間のデスクワークによって筋力が低下している人ほど、正しいフォームを意識するだけで痛みの改善が見られることもあります。
サポーターやテーピングの活用
膝の内側の痛みによっては、サポーターやテーピングを利用する対処法もあります。
特に「少し歩くだけでも痛いが、どうしても外出しなければならない」という状況では一時的な保護として有効です。
サポーターを使うと膝周辺の筋肉や靭帯をサポートし、負担を分散してくれます。
ただし、これらはあくまで一時的なサポートに過ぎません。
根本的な改善を図るには、原因を見極めて適切な予防策やトレーニングをする必要があります。
2. 原因
 膝の内側が痛くなる原因は人それぞれで、骨や関節、筋肉や靭帯など多岐にわたります。
膝の内側が痛くなる原因は人それぞれで、骨や関節、筋肉や靭帯など多岐にわたります。
ここでは主な要因やメカニズムを分かりやすく解説します。
関節内の問題
膝関節は大腿骨と脛骨がかみ合っており、その間には半月板という軟骨組織が存在します。
半月板に損傷があると、膝を曲げ伸ばしするたびに痛みが生じ、特に内側に負担がかかる場合には内側半月板の損傷が疑われます。
スポーツだけでなく、普段の生活で体重や負荷のかかり方によってじわじわとダメージが蓄積されることもあります。
靭帯や筋肉の損傷・炎症
膝の内側をサポートしている内側側副靭帯の損傷や、膝周辺の筋肉の炎症が原因となるケースもあります。
内転筋など内ももの筋肉が弱っていると膝の安定性が低下し、内側への負担が増加します。
また、急な運動や過度なトレーニングで筋膜が炎症を起こし、痛みを発生することも少なくありません。
O脚やX脚による負担偏り
O脚やX脚の人は膝にかかる荷重が偏りやすいため、内側または外側にストレスが集中しやすい傾向があります。
O脚の場合は内側が圧迫される形になりやすく、立ち仕事や歩行時の衝撃が内側の軟骨や靭帯に大きくかかることがあります。
加齢や運動不足による衰え
運動不足や加齢によって筋力が低下すると、膝関節をサポートする力が弱くなり、結果として余分な負担がかかります。
特にデスクワークが多い方は、膝の曲げ伸ばしをあまりしない日常が続くことで、筋肉の柔軟性が失われ、痛みが出やすくなります。
階段の上り下りやちょっとした移動でも負担が大きくなり、内側に痛みが集中する場合が多いのです。
体重増加や姿勢の乱れ
体重増加は膝への負担そのものを増大させます。
また、姿勢の乱れがある状態だと、体重がスムーズに足裏全体へ分散されず、一部(特に内側)に荷重がかかりやすくなります。
体重と姿勢は膝の健康に大きく影響するので、日常的にチェックすることが大切です。
3. 予防
 対処法だけでなく、今後も膝の内側の痛みに悩まされないようにするための予防策も重要です。
対処法だけでなく、今後も膝の内側の痛みに悩まされないようにするための予防策も重要です。
痛みが出る前から対策を講じることで、慢性化を防ぎ、快適な日常生活を維持できます。
適度な運動で筋力を維持
膝を安定させる筋肉は、大腿四頭筋(太ももの前)やハムストリングス(太ももの裏)、内転筋(内もも)など多岐にわたります。
これらの筋肉をバランスよく鍛えることで、膝関節が安定し、内側だけに負担が偏る状況を防げます。
ウォーキングや軽いジョギング、水中ウォーキングなど、膝への衝撃が比較的少ない運動を継続すると良いでしょう。
定期的なストレッチとケア
筋肉は一度硬くなると、自分の意志だけで完全に柔らかくするのは難しい面があります。
日常的にストレッチを取り入れると、筋肉の柔軟性と血流が向上し、関節への負担が軽減されます。
特にデスクワークの場合、1時間に一度は軽く立ち上がって膝や太ももを伸ばすだけでも効果的です。
さらに、入浴後や就寝前に軽いマッサージを取り入れてみてください。
筋肉が温まっているタイミングで、膝周辺や太ももを優しくさすり、硬くなった部位をほぐすと血行促進につながります。
正しい姿勢・歩き方を習慣化
骨格や筋肉の使い方が偏っていると、膝の内側に痛みが集中しやすくなります。
前述したように、かかと→足裏全体→つま先という重心移動を意識する歩き方を習慣化しましょう。
意識が薄れるとすぐに元の癖に戻ってしまうこともあるため、最初は「通勤中に3分だけ意識する」など小さなステップから始めるのがおすすめです。
デスクワーク中の姿勢についても、定期的に自分の身体の状態を見直してください。
椅子に浅く座っていないか、猫背になっていないか、机と椅子の高さが合っているかなどをチェックし、都度修正していくことが大切です。
体重コントロール
体重が増加すると膝全体への負荷は増大し、内側へのストレスも大きくなります。
急激なダイエットは健康を害する恐れがあるため、バランスの良い食事と適度な運動を心がけ、少しずつ体重を落としていくことが理想的です。
特にデスクワークで活動量が少なくなりがちな方は、日常的にこまめな動きを増やすと同時に食生活を見直すと良いでしょう。
4. 継続するためのコツ

一度ストレッチや運動を始めても、忙しさや疲れなどを理由に長続きしないことが多いのではないでしょうか。
しかし、膝の内側の痛みを予防・改善するには継続が不可欠です。
ここでは継続のポイントをお伝えします。
無理な目標を設定しない
最初に高い目標を設定してしまうと、達成できなかったときにモチベーションが急降下しがちです。
忙しい方ほど「毎日1時間運動」というのは現実的ではない場合が多いでしょう。
まずは「1日5分から」「週2回だけ」など、負担にならない範囲で続けられる目標を設定してください。
段階的にハードルを上げていくことで、成功体験を積み重ねながら自然とモチベーションを維持できます。
ルーティン化して意識の外で行う
日常の一部に組み込んでしまう方法は、継続しやすい代表的なコツです。
たとえば「朝起きたら軽いストレッチをする」「通勤前に駅まで1区間分だけ歩く」「昼休みにイスで座ったまま太ももの裏を伸ばす」など、特別なことではなく“ついで”感覚でできる行動をプラスしてみましょう。
少しずつでも継続することで、膝に良い習慣が定着します。
記録をつけて自分の進歩を確認
スマートフォンのアプリや手書きの日記など、なんらかの形でストレッチや運動の記録を残すのも有効な手段です。
「今日は5分だけ」「ウォーキングを10分やった」といった小さな成果でも、数字や文字で目に見える形にすると達成感が得られます。
また、痛みの度合いを「今日は10段階中で痛みレベル3だった」というふうにメモしておくと、後から振り返ったときに改善傾向を実感しやすくなります。
合わない方法はすぐに見直す
ストレッチや運動方法は人それぞれの体型や体力レベルに左右されます。
自己流でやって膝が悪化したり、続けるのが苦痛になったりするのであれば、別の方法を探すのもひとつの手です。
必ずしも流行のトレーニングが自分に合っているとは限りません。
自分の身体の反応をきちんとチェックしながら進めていくことが重要です。
5. どうしても解決できない場合は早めに専門家へ相談

膝の内側の痛みが続いたり、何度も再発を繰り返したりする場合は、早めの専門家への相談をおすすめします。
放置して悪化すると、歩行困難などの深刻な状態になりかねません。
特に以下のような症状や経過がある場合は、医療機関や整体、ストレッチ専門家などの助けを積極的に借りましょう。
• 痛みが急激に強くなり、日常生活に支障が出る
仕事での移動や通勤すら困難になっているなら、迷わず専門家に診てもらうのが賢明です。
• 関節が引っかかるような感覚がある
半月板損傷などが疑われ、専門的な検査が必要なケースもあります。画像検査(MRIなど)が必要になることも。
• 痛みが長期間改善しない
自己流のケアを試しても痛みが引かず、数週間・数ヶ月単位で慢性化している場合は、根本的な原因を特定する必要があります。
どこに相談すべきか
• 医療機関(整形外科)
まずは医師による診断が必要と考えられる場合に行きましょう。
画像診断や検査を通じて、骨や軟骨、靭帯等の状態を正確に把握できます。
必要に応じて投薬やリハビリなど専門的な処置を受けられます。
• 整体院や整骨院
骨格や筋肉のバランスを調整しながら、痛みの原因を探ってもらう方法です。
柔道整復師や鍼灸師が在籍している施設も多く、慢性的な痛みに対してもアプローチが期待できます。
ただし、施術が自分の症状に合っているか見極める必要があるので、評判や施術内容を事前に確認しましょう。
• ストレッチの専門家(パーソナルトレーナーやトレーニングジム)
近年は膝や腰など部位別の悩みに特化したパーソナルジムやストレッチ専門店が増えています。
トレーナーによる個別指導を受けることで、日常生活でのストレッチや筋トレ方法を正しく学べます。
忙しい方でも短時間で集中してケアを行えるのが大きなメリットです。
まとめ

対処法
• 冷却や温めで痛みをコントロール
• デスクワークでもできる簡単なストレッチ
• 姿勢や歩き方の見直し
• サポーターやテーピングの一時的活用
膝の内側が痛いときにまず試してほしいのが、炎症を抑えるための冷却と血行を促進するための温めです。
痛みが緩和してきたら、負担を減らす正しいフォームやストレッチを積極的に取り入れましょう。
原因
• 関節内の問題(半月板損傷など)
• 靭帯や筋肉の炎症・損傷
• O脚やX脚など骨格の歪み
• 運動不足や加齢による筋力低下
• 体重増加や姿勢の乱れ
膝の内側痛は複数の要因が重なって起こることが多いです。
まずは原因を正確に把握し、適切なケアを行うことが重要です。
予防
• 適度な運動で筋力を維持
• 定期的なストレッチとケア
• 正しい姿勢・歩き方の習慣化
• 体重コントロール
予防の基本は、筋肉をバランス良く鍛え、膝への負担を軽減すること。
デスクワーク中心の方ほど、隙間時間を活用したり生活習慣を見直すだけで効果を実感しやすくなります。
継続するためのコツ
• 無理な目標を設定しない
• ルーティン化して意識の外で行う
• 記録をつけて進歩を確認
• 合わない方法はすぐに見直す
膝の痛み改善には継続が何よりも大切です。
無理なく続けられる形で習慣化し、小さな成功体験を積み重ねることで結果的に大きな改善につながります。
どうしても解決できない場合は早めに専門家へ相談
• 痛みが強く、日常生活に支障が出る
• 関節が引っかかる感覚がある
• 痛みが長期間改善しない
• 医療機関、整体、ストレッチ専門家などに相談
自分で対処できる範囲を超えていると感じたら、適切な専門家に相談して根本的な原因を突き止め、最適な治療やケアを受けましょう。
膝の内側の痛みを放置すると、日常動作や生産性にも大きな影響を及ぼします。
とくにデスクワークで長時間座りっぱなしの方ほど、日々の小さなケアを怠ると痛みが慢性化しやすい傾向があります。
まずは痛みが出たときにできる対処法から始め、原因や予防をしっかりと理解して継続的にケアを続けてみてください。
それでも改善しない、もしくは痛みが増していると感じた場合には、医療機関や整体、ストレッチの専門家などへ早めに足を運ぶことが大切です。
正しい知識と継続的なケアがあれば、膝の不安を減らし、快適に日常生活を送ることができるはずです。
あなたの膝が少しでも楽になり、生産性を落とすことなく健康的な生活を送れるよう、ぜひこの記事を参考に、今日から実践してみてください。
では、痛みのない快適な暮らしを目指して、一歩ずつ始めていきましょう!
参考文献
- WHO(世界保健機関). Osteoarthritis – Fact sheet
- 厚生労働省. 健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023(最新版PDF)
- 日本整形外科学会/Minds. 変形性膝関節症 診療ガイドライン2023(概要ページ)
- Cochrane(系統的レビュー). Is exercise an effective therapy to treat knee osteoarthritis?(2024更新)
- American Academy of Orthopaedic Surgeons(AAOS). Meniscus Tears(半月板損傷)