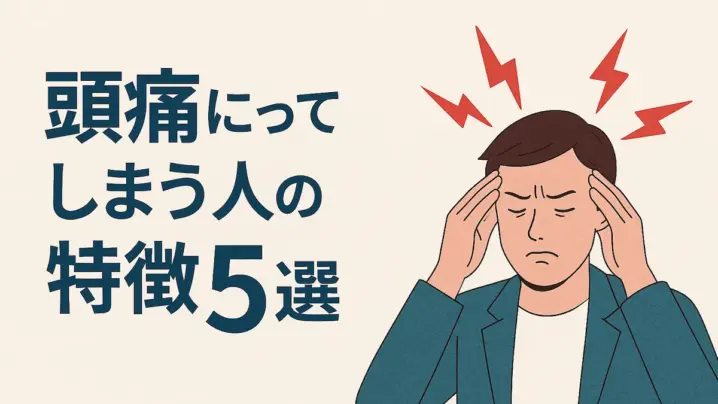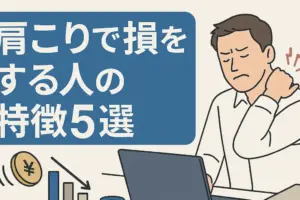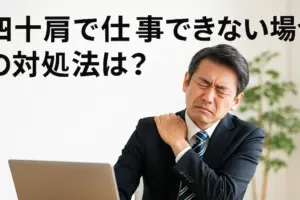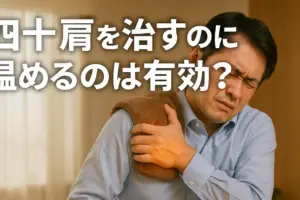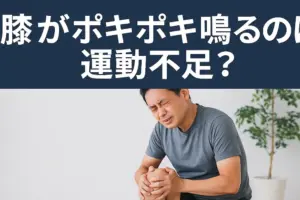朝イチのオンライン会議でこめかみがズキッ…そんな経験はありませんか?
結論をいうと、頭痛に悩む人には共通する生活習慣が潜んでいます。
実は…姿勢や呼吸のちょっとしたクセが首と脳の血流を滞らせていると言われています。
この記事では、ストレッチの専門家が頭痛になってしまう人の特徴と今すぐできる改善策を徹底解説します。
………………………………………………………….
目次(Contents)
【特徴1】スマホ首(ストレートネック)を放置している

デスクワーカーが最も長い時間を費やすのはディスプレイを見つめる姿勢だと言われています。
その中でもスマートフォンを顔より下に構えて覗き込む姿勢は、頭の重さを首の後ろ側だけで受け止める状態を生み、首周辺の筋肉が常に引き伸ばされることでこわばりが蓄積すると理想とされています。
この状態が続くと、僧帽筋と肩甲挙筋がこり固まり、脳へ向かう血流がスムーズに流れなくなると言われています。
また、目線が下がることで呼吸補助筋である胸鎖乳突筋も過度に働き、呼吸そのものが浅くなりやすく、体内の酸素供給が不足して脳の疲労感を高めてしまうと考えられています。
さらに、スマホ首の方は肩関節が内側へ巻き込まれるいわゆる巻き肩姿勢になりやすく、肩甲骨の動きが制限されるため血行不良が慢性化しやすいと言われています。
すると、ちょっとした音や光にも神経が過敏に反応しやすい状態が続き、頭痛の引き金が日常に散らばる形になります。
一方で、首の自然なカーブを保てている人は、頭を重力線上に乗せているので筋肉の余計な緊張が起こりにくく、長時間の作業でも肩こりや頭痛が起こりにくいとされています。
今すぐできる改善アクション
- 画面は目線の高さに:ノートPCやスマートフォンの下に台を置き、目線が落ちない高さへ調整しましょう。
- 30分に一度、背骨を真っ直ぐに伸ばし、首を真上に引き上げるイメージで深呼吸を3回行いましょう。
- 退社前に30秒間、後頭部を両手で支えて軽く押し返すアイソメトリックのエクササイズを行うと良いと言われています。
加えて、リモート会議の際にスマホを手持ちでメモ代わりに使う方は要注意です。
テーブルに置いたまま覗き込む角度を繰り返すと、夕方頃には肩の外側が板のように張りつめる感覚に悩まされるケースが多いと言われています。
さらに帰宅後にスマホで動画視聴をする際も同じ姿勢になるため、一日の終わりには首まわりの筋肉が完全にオーバーワークとなります。
ビジネスシーンではスマホスタンドや外部ディスプレイを活用し、視線が一点に集中しない工夫が推奨されています。
ビジネスシューズの踵がすり減っている場合、重心が前に傾きスマホ首を助長するとも言われています。
月1回靴底をチェックし、左右差が大きい場合はインソールで補正するだけでも首への負担が軽減すると考えられています。
ポイントは「画面は目の高さ」「こまめなリセット」「首を前に倒さない」の3つ。朝に1度意識するだけで1日の姿勢が大きく変わると言われています。
【特徴2】呼吸が浅く、胸郭がほとんど動いていない

キーボードに手を置いたまま肩をすくめた姿勢を続けていると、横隔膜の動きが制限され胸郭が前後にも横にも広がりにくくなると言われています。
呼吸が浅い状態では血液に取り込まれる酸素量が低下し、脳が早い段階で疲労を感じ、集中力が切れるたびにこめかみ周囲の筋緊張が高まりやすいと理想とされています。
また、浅い呼吸は交感神経を優位にし、ストレスホルモンの分泌が高まりやすく、光や音に過敏に反応する頭痛体質を強化すると考えられています。
ありがちなシチュエーション
・急ぎのメール作成で肩甲骨が固定されたまま早打ちを続ける
・イヤホン会議で肩を上げ気味に音量を聞き取ろうとするクセ
・プレゼン前の緊張で息を止め気味になり、やがてこめかみが脈打つような重さを感じる
今すぐできる改善アクション
- 吸う息で鼻から3秒、吐く息で口から6秒の比率を意識するとリズムが整うと言われています。
- 椅子に座ったまま両手を頭上に伸ばし、肋骨の側面を広げるように深呼吸を3回行いましょう。
- 会議が始まる前に「息を最後まで吐き切る」ことを意識すると、スムーズな呼吸サイクルに戻りやすいとされています。
呼吸の浅さは姿勢の悪化とも連動しています。
デスクワークで骨盤が後傾し背中が丸まると、横隔膜が縮こまり肋骨が下方へ押し潰されるようになります。
この状態では肺が膨らむスペースが少なくなり、深い呼吸が困難になると言われています。
胸郭を大きく使った深呼吸は副交感神経を優位にし、頭痛の根底にあるストレス反応を静める働きが理想とされています。
ビジネスシーンでの応用ヒント
・ウェブ会議の待ち時間中に背筋を起こし、肋骨を360度膨らませるイメージで3回呼吸を行いましょう。
・メールチェックの前後にタオルを背中に当て胸を広げるリセットタイムを設けると効率的と言われています。
・午後の眠気にはカフェイン追加より「鼻から吸い、長く吐く」呼吸法を試すと脳への酸素供給が回復するとされています。
呼吸はリズムであると言われています。
社内チャットの通知音が鳴るたびに一度息を吐く「通知デトックス呼吸」を習慣にすると、浅い呼吸からの脱却がスムーズになるでしょう。
呼吸が深まると血中の酸素飽和度が上がり、首の筋肉が二次的に緩むと言われています。
定期的に胸郭を動かすことで、午後の頭痛リスクを下げるだけでなく声の通りも良くなり、プレゼンの説得力が増す効果が期待できるでしょう。
【特徴3】水分不足とカフェイン過多を引き起こしている

コーヒーを片手に進む朝のルーティンは働くモチベーションを上げると言われています。
しかし、カフェインは利尿作用を高め、体内の水分を排出しやすくするため、血液の粘度が高まり脳の循環効率が落ちると考えられています。
「頭が重い」「こめかみが脈打つ」と感じる頃には、体が軽い脱水状態に傾いているケースが多いと言われています。
ありがちなシチュエーション
・朝から2杯目のコーヒーを終え、昼食まで水をほとんど飲んでいない
・会議中に飲むのはホットコーヒーかエナジードリンクで、常温の水を後回しにする
・午後の眠気対策にカフェインタブレットを追加し、結果的に500ml以上の水が不足する
水分不足が頭痛を招くメカニズムは、血液量の減少により脳へ流れる酸素と栄養が不足し、脳が拡張型の血管反射を起こして緊張状態になると説明されています。
さらにカフェイン代謝の過程で副腎が刺激されストレスホルモンが放出されると、交感神経が過剰に高まり筋肉が硬直し、首と肩のこわばりを強めると理想とされています。
今すぐできる改善アクション
- デスクに500mlのマイボトルを常備し、午前と午後で1本ずつ飲み切る習慣を持ちましょう。
- コーヒーを飲んだら同量の水をセットで摂ると、体内の水分バランスが保たれると言われています。
- 味気なく感じる場合はカフェインレスのハーブティーや常温の麦茶でミネラル補給を行うと良いとされています。
ビジネスシーンでの応用ヒント
・会議のアジェンダに「ウォーターブレイク」を挟み、全員で立ち上がって水分補給と軽いストレッチを行う文化を導入すると集中力が維持しやすいと言われています。
・メールの署名の下に「まずは一口の水をどうぞ」という自分向けリマインドを入れると、送信ボタンを押すたびに水分補給を思い出せるでしょう。
・コンビニで買うドリンクを「カフェラテ→炭酸水」に置き換えることで、カロリーとカフェインの両方を控えつつ水分量を上げることが期待されています。
水分摂取をゲーム化し、1日の目標量に到達したらカレンダーにスタンプを押すとモチベーションを保ちやすいと言われています。
血液がサラサラに近づけば、頭痛の前兆となる首の重さや目の奥の痛みも和らぐと言われています。
【特徴4】眼精疲労とブルーライトを放置している

一日中モニターを見つめるデスクワーカーにとって、目の酷使は避けられないと言われています。
まばたきの回数が減ることで角膜が乾燥し、視界がかすむたびに眉間やこめかみ周辺の筋肉が緊張を強めると理想とされています。
さらにLEDバックライトが発するブルーライトは網膜を刺激し続け、脳を昼間モードへ固定し夕方以降も交感神経を休ませない原因になると考えられています。
ありがちなシチュエーション
・二つのディスプレイを使い、コードと資料を左右に表示して視線を行き来させる
・休憩中もスマホでSNSをチェックし、目を全く休ませない
・帰宅後に暗い部屋で動画視聴を続け、画面の明るさと背景のコントラスト差で目を酷使する
視神経が疲労すると「目の奥がズーンと重い」感覚が首と肩の緊張を誘発し、緊張型頭痛へつながるケースが多いと言われています。
ブルーライトは睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を遅らせ、寝入りばなに脳がリラックスモードへ切り替わりにくく浅い睡眠が続いた翌朝に頭痛が再燃しやすい悪循環を生みます。
今すぐできる改善アクション
- 20分画面を見たら20秒遠くを見て、目と首の筋肉をリセットする「20-20ルール」を取り入れましょう。
- ディスプレイの色温度を暖色寄りに設定し、夜間はブルーライトカットモードをオンにすることが推奨されています。
- 仕事終わりにホットタオルで目元を温めると、副交感神経が優位になり頭痛予防に役立つと言われています。
ビジネスシーンでの応用ヒント
・社内で「まばたきリマインダー」を導入し、PCの端にポップアップを出して意識的に目を潤す習慣を作る
・照明を調光できるオフィスで夕方以降は暖色照明に切り替え、脳を夜モードへ導く環境を整える
・オンライン会議の合間にアイマスクを装着し、1分間だけ目を閉じて口回りを軽く動かすと顔全体の血流が回復すると言われています。
目の体操として、左右の視線移動に合わせて肩甲骨を開閉する「スキャプラ・アイサークル」を取り入れると、肩と目を同時にリセットできるとされています。
ブルーライトカットフィルターは一度設定すれば効果が持続する「レバレッジ行動」として忙しいビジネスパーソンに特におすすめです。
目を守ることは頭痛対策の要とも言われています。
【特徴5】睡眠の質を軽視し、就寝前もスクリーンを見続けている

頭痛と睡眠不足の関係は切っても切り離せないと言われています。
夜遅くまでスマホやノートPCの画面を凝視していると、脳は「まだ昼」と勘違いし睡眠ホルモンのリズムが乱れて寝つきが悪くなると理想とされています。
浅い睡眠が続けば身体の修復が進まず、翌朝には首肩のこわばりと共に重い頭痛が再燃しやすい悪循環が生まれます。
ありがちなシチュエーション
・ベッドに入ってからSNSをスクロールし、気づけば30分経過
・仕事のメールチェックを「念のため」で開き、緊急対応に追われて就寝時刻が後ろ倒し
・寝る直前に刺激的な動画を視聴し、脳が興奮したまま布団に入る
睡眠不足が頭痛を招くメカニズムは、脳脊髄液の循環が滞り老廃物が蓄積し神経が過敏になると説明されています。
また、疲労回復に重要な深い睡眠が短くなることで筋肉の緊張が取れず、首と肩の血行が改善しにくい状態が続くと言われています。
今すぐできる改善アクション
- 就寝1時間前からスマホを手の届かない場所に置き、代わりに紙の本やストレッチボールを手に取る習慣をつけましょう。
- 寝室の照明を間接照明に切り替え、色温度を暖色に設定するとリラックスしやすいとされています。
- 布団に入る前に「鼻から4秒吸って、口から8秒吐く」呼気長めの呼吸を5回行うと入眠がスムーズと言われています。
ビジネスシーンでの応用ヒント
・翌日のタスクを書き出し可視化することで就寝時の思考ループを防げると言われています。
・勤務終了後のメールチェックはタイムリミットを設け「19時以降は確認しない曜日」を決めると睡眠の質が劇的に向上する事例が多いと言われています。
自宅でできるセルフケア
・寝室のカーテンを遮光性の高いものに替え、外光による浅い覚醒を防ぐと深い睡眠が得られるとされています。
・夕食後は温かいハーブティーを選び消化が落ち着いてから入浴すると入眠のタイミングが整いやすいでしょう。
・就寝15分前の軽い肩甲骨ストレッチは首と頭への血流をスムーズにし「寝落ち頭痛」の予防に役立つと言われています。
睡眠の質を可視化するスマートウォッチを活用し、深い睡眠時間が増えた日は自分に小さなご褒美を設定すると習慣が継続しやすいと言われています。
日曜夜は翌週のタスク整理を済ませたうえで、照明を落としたリビングで軽い体幹ストレッチを行うと月曜の朝に頭痛が起きにくいと語られることがあります。
そして、週末だけでもデジタルデトックスを取り入れることで脳と目をリセットし、頭痛の再発を防ぐ土台を作ることが推奨されています。
専門家へ相談するという選択肢

セルフケアを続けても頭痛が日常的に続く場合は、専門家へ相談することが推奨されています。
まず医療機関では画像検査や薬物療法を通じて重大な疾患が隠れていないか確認してもらえると言われています。
次に、整体は全身の筋肉バランスを整え首と肩の柔軟性を高めるアプローチで知られています。
ただし、整体師の技術はピンキリであるため、口コミや評判をよく調べ、ご自身が信頼をおける施術者を選択しましょう。
ストレッチ専門店やパーソナルトレーナーは筋肉の柔軟性を引き出すだけでなく、正しい姿勢をキープするための身体感覚を養う場として活用されています。相談先を選ぶ際は「頭痛の原因を多角的に捉えてくれるか」を基準にすることが大切です。単なるリラクゼーションではなく、仕事環境や生活リズムに合わせたアドバイスを受けることで日常に落とし込める改善策が増え、頭痛の再発を防ぎやすくなるでしょう。
相談前に準備しておくと良いポイント
・頭痛が起きる時間帯と状況をメモしておくと専門家が原因を絞り込みやすいと言われています。
・普段のデスク環境や椅子の高さ、モニター位置の写真を持参すると姿勢指導の精度が上がるでしょう。
・水分摂取量や睡眠時間を記録しておくと生活習慣の改善プランが立てやすくなるとされています。
医療機関・整体・ストレッチの連携活用
医療機関で重大な病気の可能性を除外した後、整体で骨格や筋膜の緊張を調整し、ストレッチ指導で正しい動きを学ぶという三段階のアプローチは再発リスクを最小化すると考えられています。
それぞれの専門家が提供する視点を組み合わせることで「痛みの原因が不明のまま通い続ける」状況を回避できるでしょう。
お金と時間の投資バランス
検査費用や施術料は決して安くありませんが、頭痛で集中できない時間や誤ったセルフケアで遠回りする労力を考えると、短期間で原因を特定し正しい改善策を手に入れるほうが長期的にはコストパフォーマンスに優れると言われています。
相談後のセルフメンテナンス
専門家から得たアドバイスを「習慣化しやすい小さな行動」に分解し、デスク周りにリマインダーを設置するのがポイントです。オンラインで整体やストレッチのカウンセリングを受けるサービスも増えており、移動時間ゼロで専門知識を得られる選択肢として注目されています。
ケース別おすすめルート
・「昼過ぎに脈打つような頭痛が来る」→内科で血圧・脳の検査→整体で姿勢評価→ストレッチ指導が推奨されています。
・「朝起きた瞬間から頭が重い」→睡眠専門外来で検査→ストレッチで呼吸エクササイズを学ぶケースが多いと言われています。
相談先を決めたら「最低3回は継続してみる」心構えが重要です。
オンライン診療や姿勢分析アプリを併用し、経過を共有すると改善速度が上がると言われています。
まとめ

以下に、記事内で取り上げたポイントを初心者にもわかりやすく整理します。
【特徴1】スマホ首(ストレートネック)を放置している
・画面は目線の高さに、30分ごとに姿勢リセット
・首の自然なカーブを守ることで血流を改善
【特徴2】呼吸が浅い
・横隔膜を大きく動かす深呼吸を習慣化
・胸郭を広げて交感神経の高ぶりを抑える
【特徴3】水分不足とカフェイン過多
・コーヒー1杯につき同量の水でバランスを取る
・常温のミネラルウォーターやハーブティーを活用
【特徴4】眼精疲労とブルーライト
・20-20ルールと暖色照明で目と脳をリセット
・ホットタオルで副交感神経を優位に
【特徴5】睡眠の質の軽視
・就寝前はスマホを遠ざけ、呼吸を長くゆったり
・遮光と間接照明で深い睡眠をサポート
専門家へ相談
・医療機関で重大疾患の除外
・整体で全身バランスを調整
・ストレッチ指導で正しい動きを習得
ただし、整体師の技術はピンキリであるため、口コミや評判をよく調べ、ご自身が信頼をおける施術者を選択しましょう。
行動に移すコツ
・喉が渇く前に水を飲む
・画面を見たら遠くを見る
・就寝1時間前から照明を落とす
今すぐ始める3ステップ
- デスク環境を見直し、モニターの高さと椅子の位置を調整する
- スケジュール帳に「水を飲む」「深呼吸」のリマインダーをセットして行動を自動化する
- 就寝前30分はスマホを遠ざけ、軽いストレッチで体と心をリセットする
頭痛は「付き合うもの」ではなく「手放せるもの」です。
行動を変えるたびに体は必ず応えてくれると言われています。
できることから一歩を踏み出し、クリアな視界と軽い頭で仕事に没頭できる日々を取り戻しましょう。
さあ、今日のあなたには痛みに振り回されない新しい選択肢が待っています。
参考文献
- WHO「Migraine and other headache disorders」(2024) ― 頭痛の定義・種類・有病率・基礎知識。
- 厚生労働省 e-ヘルスネット「快眠と生活習慣」(2025) ― 光・ブルーライトと体内時計、就寝前の光環境調整。
- 日本神経学会『頭痛の診療ガイドライン 2021』 ― 一次性・二次性頭痛の診断と基本対応。
- Chang et al., PNAS (2015)「就寝前の発光eリーダー使用は睡眠・概日位相・翌朝の覚醒に悪影響」 ― 画面光の睡眠影響の実験的エビデンス。
- Zduńska et al., 2023「カフェインと頭痛:有用性とリスクの概説」 ― カフェイン摂取と頭痛(誘発/鎮痛)の両面を整理。