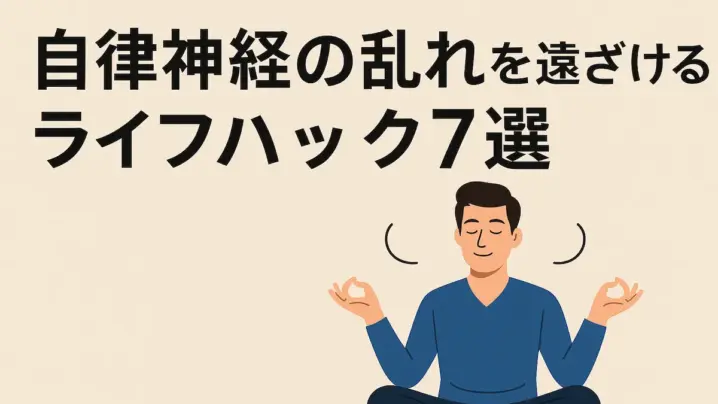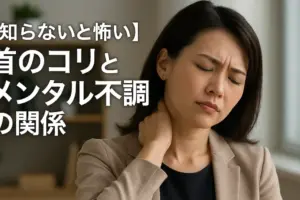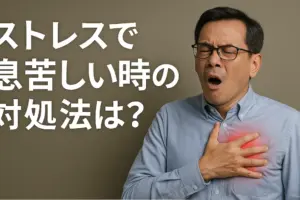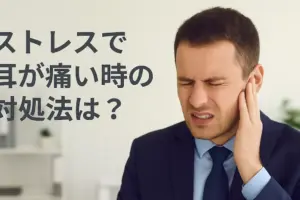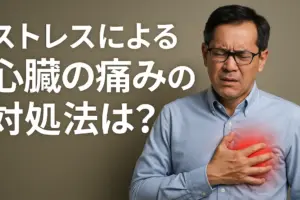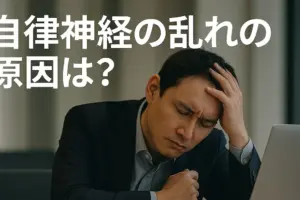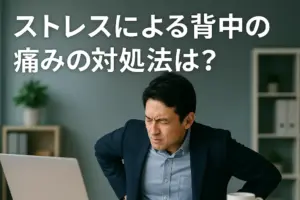集中力が急に切れたり、理由もなくイライラした経験はありませんか?
結論をいうと、短時間ストレッチと呼吸を組み込むだけで自律神経は整います。
実は…デスクワーカーこそ“動いて休む”工夫が最強の特効薬。
この記事では、ストレッチの専門家がライフハック7選を徹底解説します。
………………………………………………………….
目次(Contents)
1. 朝イチ3分ストレッチで自律神経をスムーズに切り替える

朝起きてすぐ、まだ頭がぼんやりしているタイミングこそ、自律神経をリセットするゴールデンタイムです。布団の中でスマホを開く前に、まずは大きく背伸びをし、横隔膜を意識して3回深呼吸しましょう。その後、立ち上がって両腕を肩の高さで前に伸ばし、手のひらを上に向けたまま拳を軽く握り、肩甲骨を寄せるようにして3秒キープ。この動作を10回行うだけで交感神経が穏やかに活性化し、血圧や心拍数が急上昇するのを防ぎます。
デスクワーカーの朝は、前日の残った疲労やメールチェックのプレッシャーで交感神経が優位になりすぎがちです。しかし、背伸びと腕伸ばしというシンプルな2ステップを挟むことで、身体が「安全モード」から「活動モード」へ段階的に移行します。ポイントは「痛気持ちいい強度」。筋肉を伸ばし切るより七、八割の伸長感で止めると、筋紡錘の防御反射を抑え、スムーズに副交感神経から交感神経へのバトンタッチが進みます。
さらに、ストレッチと合わせて常温の白湯250mlをゆっくり飲むと、胃腸が温まり内臓への血流がアップ。消化器が動き始める信号が脳に届き、体内時計が「一日のスタートだ」と認識します。体温がじわり上がる過程で、熱放散を担当する末梢血管が開き、自律神経の振幅が大きくなるためストレス耐性も向上。「朝からダルい…」という感覚が、わずか3分のルーティンで驚くほど改善されるでしょう。
朝のストレッチは身体の「フィードフォワード制御」のスイッチを入れ、脳が先読みしてエネルギー配分を整備してくれるため、一日の後半でも疲労感が減少します。
実践のチェックリスト
- 背伸びで肋骨の間を1cm開くイメージがあるか
- 深呼吸は鼻から4秒吸い、口から8秒吐くペースを守れているか
- 両腕を伸ばす際、肩がすくまないよう耳と肩の距離を保てているか
- 3秒キープ中に腰が反らないか、腹圧を軽く入れて骨盤を中立に保てているか
これらのポイントを守ると、筋だけでなく筋膜、静脈系、リンパ系の流れも同時に改善。朝一番に体液循環が滑らかになることで、デスクワーク中の肩こりや頭重感が「そういえば出にくい」と感じるはずです。
朝イチ3分ストレッチは、自律神経のギアチェンジを安全かつ効率良く行うライフハック。深い呼吸と適度な伸張刺激を入れることで、交感神経の急発進を抑え、自分でコンディションを“整えられる身体”へシフトさせましょう。
2. ポモドーロ休憩×肩甲骨ストレッチで集中力をリセット

午前の業務が始まると、メール対応、オンライン会議、チャット通知と刺激の波が次々押し寄せ、脳は交感神経優位のアクセル全開状態になりがちです。そこで導入したいのが「ポモドーロ・テクニック」と背中周りのストレッチを掛け合わせたリセット習慣。作業25分+休憩5分を1ポモドーロとし、合計4セットで約2時間。休憩フェーズで立ち上がり、ウォールスライド(壁に背をつけ腕をY字→W字→Y字と滑らせる)を10回行えば、肩甲骨の可動域が広がり、胸椎がしなやかに動くため、酸素摂取量が上がりやすくなります。
特筆すべきは、肩甲骨ストレッチが副交感神経を“引き上げブレーキ”として機能させる点です。長時間の座位姿勢は僧帽筋や肩甲挙筋が固まり、呼吸補助筋が動きづらくなるため交感神経が優位になりっぱなし。「集中が切れた」と感じる背景には、酸素不足と交感神経過活動がセットで存在しているケースが多いのです。ウォールスライドでは胸を開く動きと肩甲骨の内旋・外旋が同時に起こり、浅くなった呼吸を即座に深い胸式呼吸へ切り替えてくれます。
また、作業25分間で飲み物をほぼ飲み切るというルールを合わせると、脳・筋組織への水分供給が途切れません。カフェイン入りドリンクが好きな方は2ポモドーロ目までとし、午後はノンカフェインに切り替えると副腎疲労を防げます。習慣化のコツとして、タイマーアプリに加え、ウォールスライド用の画像をデスクトップ壁紙に設定しておくと視覚的リマインダーになります。
水分補給×肩甲骨ストレッチの相乗効果
肩甲骨周辺には褐色脂肪細胞が多く、動かして血流を促すことで熱産生が上がり、末梢血管が開くことで自律神経の揺らぎが穏やかになります。これに水分補給を重ねると血液粘度が下がり、脳へ酸素とブドウ糖がスムーズに届くため、いわゆる「午後の眠気」も軽減。特に常温の水+天然塩ひとつまみ(電解質)を取ると、交感神経バランスを整えるミネラル補給まで一石三鳥です。
続けるためのマイクロゴール設定
ポモドーロ4セット=100分。その間にウォールスライド×4回、深呼吸×12回、常温水1リットル摂取――これを“午前のキット”としてToDoリストに書き込み、達成したらセルフスタンプを押すと、報酬系が刺激され習慣が定着しやすくなります。
3. アクティブスタンディングデスクで体内時計を整える

座りっぱなしは“新しい喫煙”と例えられるほど、自律神経にとってリスクの高い行為です。特に長時間の前傾姿勢は胸郭を圧迫し、呼吸筋を制限し、交感神経を慢性的に刺激します。そこでおすすめなのが“アクティブスタンディングデスク”――姿勢を頻繁に切り替えながら作業できる高さ可変デスクです。机の高さ設定の目安は、肘を90°曲げた位置で手首がキーボードに軽く乗る程度。モニター上端は目線より3〜5cm下にすると頸椎がニュートラルポジションを維持できます。
立位が自律神経にどう効くかというと、重力方向の変化がもたらす血圧反射が大きな役割を果たします。座位から立位へ移行すると、一時的に下肢へ血液が落ちるため脳は交感神経を刺激して血圧を維持。その後、ふくらはぎや大腿四頭筋を軽く収縮させる“マーチング”(その場足踏み)を30秒行うと、筋ポンプ作用が働いて心臓へ血液が戻り、副交感神経が再び優位になります。この“適度な揺らぎ”が自律神経をトレーニングし、ストレス耐性を向上させるのです。
60分サイクルの実践法
- 座位25分:集中力が高いタスク(企画書、コードレビューなど)
- 立位25分:メール返信やチェックリスト処理など低〜中負荷タスク
- マーチング+肩回し5分:ふくらはぎポンプと肩甲骨ほぐしでリセット
- 水分補給+眼球運動5分:視線を上下左右に動かし首周りの筋を緩める
合計60分の中で体勢と刺激を切り替えることで、体内時計(サーカディアンリズム)の中枢にある視交叉上核(SCN)が“今は活動期”と判断しやすくなります。結果として午後の血中メラトニン分泌がスムーズに低下し、夜の睡眠ホルモン分泌が強化される――つまり日中の活動と夜間の休息がきれいに分断されるわけです。
設備投資をムダにしないコツ
スタンディングデスクは高価ですが、既存のデスクに載せる昇降台タイプでも十分効果があります。重要なのは“頻繁な高さ変更”であり、立ちっぱなしを推奨しているわけではありません。Oura RingやApple Watchなどのデバイスで立位時間と心拍変動をログし、週ごとに変化を見るとモチベーションが続きやすいでしょう。
注意点
・立位作業が初めての方は、足底筋膜炎を防ぐためクッション性の高いシューズやマットを使用
・腰が反りやすいので、モニターとキーボードの位置が合わない場合はリストレストを併用
・下半身が冷えやすい季節は膝掛けやレッグウォーマーを活用
単に座らないだけでなく、姿勢変換というマイクロエクササイズを埋め込むことで、自律神経は環境変化に柔軟に対応する“しなやかさ”を獲得します。
4. 昼休みの眼精疲労ストレッチ+深呼吸で交感神経にブレーキ

デスクワーカーが陥りやすい“午後イチのだるさ”の正体は、ランチ後の血糖変動だけではありません。午前中に酷使した眼球筋・首周りの筋緊張が交感神経を刺激し続け、脳の覚醒レベルを中途半端に高めていることが多いのです。そこで昼食後の10分を使い、視線を遠近で切り替える“ペンシル・プッシュアップ”と呼ばれる眼球運動と、首のサイドストレッチを組み合わせましょう。
10分リセットプロトコル
- ペンシル・プッシュアップ:ペン先を目の高さに置き、30cm→鼻先までゆっくり近づけ、焦点を合わせたまま戻す×10回
- 首のサイドストレッチ:右手で左側頭部を包み、息を吐きながら右に傾け20秒キープ×左右
- 肩すくめ&ストン:肩を耳に近づけて2秒ホールド→一気に脱力×10回
- 深呼吸4-8法:鼻から4秒吸い、口から8秒かけて吐く×6呼吸
この流れを行うと、眼筋・後頭下筋・僧帽筋上部の緊張がほぐれ、首の交感神経節への圧迫が低減。特にペンシル・プッシュアップは輻輳と開散を繰り返すことで動眼神経系を刺激し、副交感神経が優位に傾きやすくなるとされています。
呼吸を制する者が自律神経を制す
4秒吸って8秒吐く比率は、自律神経研究の現場でも“セーフリフレックス”と呼ばれ、迷走神経を通じて副交感神経に直接アプローチします。長く吐くことで肺の中の二酸化炭素濃度が一時的に上がり、中枢神経は「リラックスして良い」と判断。これが交感神経のアクセルを緩め、午後の集中力を再チャージする余白を作ります。
デスクで目立たず行うコツ
・ペンシルはお気に入りデザインを選び、視覚的に飽きない工夫を
・PCモニターに付箋で「眼球運動!」と書き、タイムラインに同期
・Bluetoothイヤホンでリラックス音楽を流し、外部ノイズをカット
眼精疲労が脳疲労を招くメカニズム
視覚情報処理は脳全体の使用エネルギーの約半分を占めると言われています。焦点を合わせ続ける作業はカメラで例えるならレンズのモーターを回しっぱなしの状態。これが延髄にある自律神経中枢へ過剰な覚醒シグナルとして伝わり、心拍数や血圧を維持するため交感神経が頑張り続けるのです。ペンシル・プッシュアップでレンズを“ズームイン・ズームアウト”させると、モーターが休み休み動く設計に戻るため、脳が“節電モード”に切り替わります。
1週間継続で得られる変化
- 眼の乾きが減り、瞬きの回数が自然に増える
- 午後のカフェイン摂取量が1杯減る
- 首の可動域が左右合計で10度広がることも
こうした小さな変化が蓄積すると、結果として夕方の作業効率が向上し「残業せずに済んだ」という声も。自律神経は“負荷と回復のバランス”で改善するシステムなので、昼休みというタイミングを活用して“中間メンテナンス”を行うイメージで取り組みましょう。
5. 夕方ヒップヒンジ・ウィンドミルで背骨からリカバリー

長時間座りっぱなしの背中は夕方になると胸椎の伸展が失われ、交感神経が優位に振れっぱなしになります。そんな時に推奨したいのが「ヒップヒンジ・ウィンドミル」。足幅は肩幅+拳1つぶん、つま先は外へ20°。膝とつま先の向きを揃え、背筋を伸ばしたまま股関節をヒンジ(蝶番)のように折り、対角の手で地面を触るイメージで上体を回旋させます。10回×2セット行えば、胸椎の回旋と伸展が同時に刺激され、呼吸筋が解放されるため副交感神経が働きやすくなるのです。
動作のキーポイント
- 骨盤中立:腰椎過伸展を防ぎ、腹圧で体幹を安定
- 視線フォロー:上になる手の指先を追うことで頸椎も回旋
- 呼吸同期:下ろす時に吐き、上げる時に吸うリズムで行う
夕方に背骨全体を動かすと、交感神経スイッチを一度“オフ”に近い状態まで下げられ、体内のアドレナリン濃度が低下。これにより帰宅後の“だらだらスマホ時間”を減らし、家族との会話や趣味に使える“良質なオフタイム”が確保できます。さらに、胸郭の柔軟性は心拍変動の振幅(特に高周波成分)を拡大する傾向があり、ストレス性の胃痛や緊張型頭痛の軽減が期待できます。
オフィスでの実践裏技
・会議室が空いていない場合は給湯室の横スペースを活用
・膝を床につきたくない場合はヨガマット代わりにバスタオルを常備
・スーツパンツが気になる方は、股関節ヒンジ角度を浅めにして回数を3倍に
1日の締めとしてのメリット
全身の筋膜ラインが伸ばされるため、静脈血・リンパ液がスムーズに戻り、むくみ軽減にも直結。副交感神経へのシフトが早いほど、入眠潜時(布団に入ってから寝落ちするまでの時間)が短縮されるとも言われています。
失敗しがちなポイントと対策
- 腰が丸まる:股関節を引き込む感覚が弱いと腰椎屈曲が生じる。壁にお尻をタッチする“ヒップヒンジドリル”で感覚を掴んでから挑戦
- 膝が内側へ倒れる:内股になると膝関節にストレスが集中。両手を骨盤に置き、膝とつま先が同じ方向を向くか鏡で確認
- 呼吸を止める:回旋動作でバランスを取ろうと呼吸を止めがち。テンポを落として「動きを待つ呼吸」を意識する
続けるコツ
SlackやTeamsのステータスメッセージを「17:00〜ウィンドミルタイム」と固定し、リマインダーを組み込みましょう。仲間が興味を示したら一緒に実践すると、行動経済学で言う“ピア効果”が働き、継続率が2倍以上になるとされています。
胸郭の可動性向上は酸素摂取効率を支え、夕方以降の“もうひと踏ん張り”を穏やかに支援してくれるでしょう。
6. 就寝前キャット&カウ+チャイルドポーズで副交感神経優位

夜、布団に入っても思考が止まらず、スマートフォンの青い光でさらに目が冴える――そんな悪循環を断ち切る鍵は“背骨をゆらす”ことにあります。具体的には「キャット&カウを10回行いながら、背骨を丸める動作で吐く息、反らす動作で吸う息に100%意識を向ける」→「チャイルドポーズで30秒静止し呼吸を整える」という流れ。照明は暖色の間接光に落とし、テレビやPCはオフにして静かな環境を作るのがポイントです。
なぜ背骨か?
背骨の両側には多数の自律神経節が存在し、特に胸椎~腰椎の可動域が狭まると交感神経が過剰に刺激される傾向があります。キャット&カウで背骨全体を波のように動かすと、脳脊髄液の循環が促進され、頭蓋内圧が微細に変動。この振動が延髄にある迷走神経核を刺激し、副交感神経を活性化させます。さらに最後のチャイルドポーズは、腹部が大腿部に圧迫されることで横隔膜をストレッチし、呼気が深く長くなるため“眠りスイッチ”を押す追い打ちになります。
呼吸リズムの黄金比
・吸気:4秒 / 呼気:8秒
・鼻呼吸を徹底し、吐く時に喉の奥で軽く音を立てる“ウジャイ呼吸”風だとリラックス効果UP
・10呼吸で心拍数が5〜7bpm下がるのを目安に
実践環境の整え方
・ヨガマットがない場合は畳やカーペットの上でOK
・照明は2700K前後の電球色が理想。スマートライトのタイマー機能を活用
・寝間着は腹部を締め付けないコットン素材を選ぶ
就寝前に副交感神経を優位にしておくと、深睡眠(デルタ波)の割合が増え、成長ホルモン分泌が最大化されると言われています。結果として翌朝の覚醒時に“ぐっすり寝た感”が得られ、朝イチのストレッチがさらに効果的に。入眠前のルーティンは“1日のログアウト処理”と考え、PCのシャットダウンと同じくらい丁寧に行いましょう。
続けるコツとトラッキング
睡眠アプリで深睡眠時間を測定し、キャット&カウを行った日は+15分長く眠れたかなど、数字で変化を確認するとモチベーションが続きやすくなります。Apple WatchやOura Ringは心拍変動(HRV)を計測できるため、就寝前ストレッチを始めて2週間で高周波(HF)成分が増加=副交感神経活性が上がった、という結果が出ることも珍しくありません。
NG例
- ベッドの上でマットレスが沈み込み、背骨のラインが崩れてしまう
- 呼吸を意識しすぎて過呼吸気味になり、逆に交感神経が刺激される
- ストレッチ後すぐにスマホをチェックし、ブルーライトで台無しになる
最初は「たった5分で変わるの?」と半信半疑かもしれません。しかし自律神経は“繰り返す刺激”に敏感です。毎晩同じ順序・同じ時間で行うと“古いパスワードを入力せずにログインできる”ような自動化が脳内で起こり、ストレッチを始めただけで眠気スイッチが入る条件反射が形成されます。
7. 朝のリブートドリンク+全身伸びでスムーズに起動

目覚めの常温の白湯250mlに天然塩ひとつまみを混ぜた“リブートドリンク”は、寝ている間に失われた水分と電解質を素早く補給し、自律神経を“再起動”する役割を果たします。さらに、飲み終えたらその場で全身伸びを3回行い、筋肉と神経を同時に目覚めさせる――この2ステップをセットにすることで、カフェインに頼らないシャキッとした覚醒を得られるでしょう。
リブートドリンクの科学
体液の浸透圧を一定に保つナトリウムを摂取すると、体は“水分が十分入ってきた”と判断し、腎臓が尿として排出する量を抑えます。その結果、血漿量が増え、血流が良くなることで末梢血管が開きます。これが副交感神経を適度に刺激し、体温上昇を滑らかにします。ここに全身伸びの伸張刺激が加わると、交感神経が“穏やかに”アクセルを踏み、急激な心拍数上昇を防ぎながら覚醒が進むのです。
全身伸びのポイント
- 両手を頭上で組み、かかとを上げて体を一直線に伸ばす
- 伸ばし切ったところで3秒キープし、脱力→2秒休憩を3セット
- 伸びの最中は鼻から吸い、脱力した瞬間に口から吐く
エネルギーマネジメントへの効果
朝の水分・電解質・ストレッチの組み合わせは、午前中の血糖安定にも寄与します。血流が改善するとインスリン感受性が高まり、同じ朝食でも血糖ピークが緩やかに。結果として11時頃の“おやつタイム”に襲ってくる集中力低下を抑えられると感じる人が多いです。
習慣化のテクニック
- 就寝前にベッドサイドに常温水と塩入り小瓶をセット
- 目覚まし時計のスヌーズ機能を使い、1回目でドリンク、2回目で全身伸び
- ドリンク中に“今日は○○を達成する”と声に出し、脳のRAS(網様体賦活系)をオン
注意点とカスタマイズ
- 塩分制限がある方は医師に相談し、塩の量を減らすかカリウム豊富なフルーツで代用
- 冷え性の方は白湯の温度を45℃前後にして内臓を温める
- 全身伸びが難しい場合は、うつ伏せで“スフィンクスポーズ”を30秒保持してもOK
継続すると…
自律神経は“刺激の質とタイミング”に反応してアップデートされるため、起床直後というタイムスタンプを固定してルーチン化することが成功のカギ。さらに、週末だけでもリブートドリンクにレモン汁を数滴加えるとビタミンCが副腎をサポートし、ストレス耐性強化にもつながります。
専門家へ相談

自律神経の乱れを感じたとき、セルフケアだけで解決しないケースもあります。その場合は、以下の専門家を頼ると解決のスピードが一気に上がることがあります。
医療機関
内科や心療内科では、自律神経の状態を把握する心拍変動解析やホルモン検査などを通じて、医学的なアプローチを提案してくれます。睡眠障害や重度の不安症状が絡む場合は、薬物療法を含む統合的なケアが必要とされることも。「まずは大きな病気が隠れていないか確認する」という意味でも、最優先の選択肢です。
整体ストレッチ
整体のアジャスト技術による骨格調整と、パートナーストレッチで深層筋を伸ばす技術――この“いいとこ取り”を組み合わせたサービスです。一人では伸ばしきれない筋膜ラインを安全に解放し、自律神経反射を利用して全身をリラックスさせる効果が期待できます。ただし、整体師の技術はピンキリであるため、口コミや評判をよく調べ、ご自身が信頼をおける施術者を選択しましょう。
パーソナルトレーナー
姿勢改善と運動習慣の継続を同時に叶えたい方は、パーソナルトレーナーが有効です。フォームチェックや負荷管理を行いながら、あなたの可動域・筋力レベルに合わせたストレッチ&トレーニングプランを提供してくれます。特にオンライン指導も増えているため、忙しいビジネスパーソンでも始めやすいのが魅力。費用はかかりますが、“習慣化の外部化”として投資効果は高めです。
相談の際のチェックポイント
- 専門家の経歴やレビューを必ず複数サイトで照合
- 初回カウンセリング時にゴールや悩みを具体的に伝える
- “セルフケアで得た効果”と“まだ残る課題”をメモして持参
価格だけで判断せず、“成果の再現性”や“フィードバックの質”に注目してください。特に整体ストレッチとトレーナーは、人対人のサービスです。相性が合わないとモチベーションが下がり、結果としてコスパも悪化します。
オンラインvs対面
医療機関でも遠隔モニタリングやチャット相談が普及し、自律神経ケアのハードルは下がり続けています。ただし、背骨や骨盤の歪みをダイレクトに調整する整体ストレッチは、やはり対面の方が効果的という声が多数。オンラインで情報収集し、対面で仕上げるハイブリッド型も検討してみてください。
相談前に整えておくセルフデータ
- 睡眠時間・中途覚醒回数
- 食事時間と内容、カフェイン摂取量
- 1日の座位・立位・歩数の比率
- ストレッチ実施の有無と簡易メモ
これらをアプリや手書きノートで可視化すると、専門家が原因を特定しやすく、あなた自身も改善度合いを追跡できます。
自律神経は“生活全体を映す鏡”なので、セルフケアと専門家サポートを上手に組み合わせるほど、回復スピードが飛躍的に上がります。「もう少し早く相談すれば良かった」と後悔しないよう、気になる症状が続く場合は早めにプロの扉をノックしましょう。
まとめ:自律神経を整える7つのライフハック総復習

- ライフハック1 朝イチ3分ストレッチ
- 背伸び+腕伸ばしで交感神経を穏やかに起動
- 白湯を合わせて体温と血流を同時に上げる
- ライフハック2 ポモドーロ休憩×肩甲骨ストレッチ
- ウォールスライドで呼吸筋を解放し集中力を再チャージ
- 常温水+天然塩で血液循環とミネラル補給
- ライフハック3 アクティブスタンディングデスク
- 立位と座位を60分周期で切り替え体内時計をリセット
- マーチング30秒で下肢ポンプを作動させる
- ライフハック4 眼精疲労ストレッチ+深呼吸
- ペンシル・プッシュアップで視覚ストレスを解放
- 4-8呼吸で副交感神経にブレーキ
- ライフハック5 ヒップヒンジ・ウィンドミル
- 胸椎の伸展と回旋で夕方の交感神経過活動をリセット
- 帰宅後のリラックスとむくみ軽減をサポート
- ライフハック6 キャット&カウ+チャイルドポーズ
- 背骨の波運動で脳脊髄液循環を促進し入眠準備
- 呼吸を4:8に整え深睡眠をブースト
- ライフハック7 リブートドリンク+全身伸び
- 水分+電解質+伸張刺激で朝の覚醒を穏やかに加速
- 血糖の安定と集中力持続に寄与
これら7つのライフハックを“朝・昼・夕・夜”のタイムラインに組み込めば、自律神経は揺らぎながらも安定したリズムを刻み始めます。完璧を目指すより“1つずつ積み重ねる”ことが成功の近道。困ったときは医療機関・整体ストレッチ・パーソナルトレーナーという3つの専門家を賢く活用し、あなたの“整った毎日”をデザインしてください。
参考文献
- 厚生労働省. 情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン
- World Health Organization. WHO Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour (2020)
- Laborde S, Mosley E, et al. Effects of voluntary slow breathing on heart rate variability: A systematic review and meta-analysis. Neuroscience & Biobehavioral Reviews. 2022.
- Albulescu P, Iacob LL, et al. “Give me a break!”: A systematic review and meta-analysis on the efficacy of micro-breaks for increasing well-being and performance. PLOS ONE. 2022.
- 公益社団法人 日本眼科医会. パソコンと目(VDT作業と眼精疲労)